
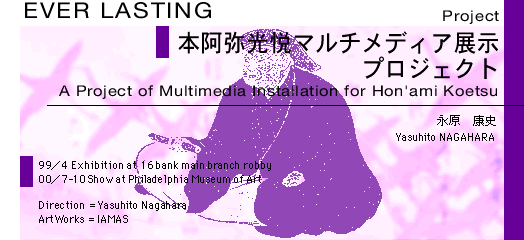

本プロジェクトは、日本の伝統的な美術工芸を、マルチメディアを用いた新たな手法で展示する試みであり、フィラデルフィア美術館の本阿弥光悦展覧会と関連して企画された。
例えば、巻子は作品を“手にとって見る”という行為そのものにも重要な意味を持つが、今日では陳列ケースの中で一部分しか目にすることができず、アメリカ人だけではなく日本人にも本来の有様を知り、体験することは難しい状況にある。しかし、ディスプレイ上に解説や関連する画像も自由に取り出すことができるヴァーチャルな和歌巻を設定すれば、巻子に施された和歌や下絵を自分のペースで巻きながら楽しむことができ、描かれている内容についても様々な角度からの理解が可能だ。このように鑑賞法に幅を持たせることで、作品についてより多くの情報を得ることができ、観覧者に興味と理解を導く糸口となる。
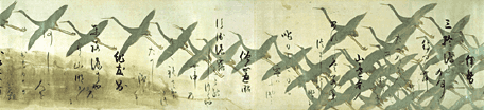

「鶴下絵三十六歌仙和歌巻」(京都国立博物館蔵)
紙本金銀泥下絵墨書
34.0×1356.7 cm
「光悦」黒文方印



日本の伝統的な工芸品は、実用性と鑑賞性を兼ね備えたものとしてつくられてきた。 それらは、保存のため、展示される機会も限られている上に、展示されたものは手に ふれることができず、工芸美術本来の鑑賞法とは大きく異なるものになっている。 例えば、巻子の場合だと、手にとって繰りながら見る(読む)のが本来の使い方(鑑 賞法)であるにも関わらず、展示された陳列ケースの中でしか見ることができない。 このプロジェクトでは、まず巻子の操作方法を提示することにより、本来のメディアとしての巻子を体験できるようにした。
過去の工芸作品をデジタル化する場合、作品を再現するデータそのものに価値を見い出すことができるだろう。そのデータは、物であるレプリカとは異なり、あくまでも、本物に対する模型、モデルとして提示することが可能だ。モデルであることは、鑑賞者にとって、本物との距離を知る手がかりになるだろう。もし、本物そっくりのレプリカをつくってしまったなら、それもやはり本物と同じように優れた工芸品 という道をたどってしまうしかないのだから。
ここでは純粋に鑑賞する行為だけを本来の物から受け継ぎ、鑑賞者はその行為を体験 することになる。鑑賞者は、本物の工芸作品とはちがったその展示に工芸品本来の鑑 賞法と自分なりの接し方を見つけ、その工芸品がかつてそうされたであろう記憶を呼びさますことができるのだ。(談:永原康史、構成:原田史帆)


茶碗鑑賞のための装置。実際の茶碗の3Dデータをモニタ上に再現している。鑑賞者は模型の茶碗をインターフェイスとして手にとり、モニタ上の茶碗を様々な角度から見ることができる。
-
本阿弥光悦マルチメディア展示プロジェクト実行委員会
代表=フェリス・フィッシャー
顧問=梶原 拓(岐阜県知事)
清水義之(株式会社十六銀行頭取)
アン・ダノンコート(フィラデルフィア美術館長)
委員=狩野博幸(京都国立博物館学芸課美術室長)
名児耶明(五島美術館学芸部長)
坂根厳夫(IAMAS学長)
永原康史(アートディレクター、IAMAS教授)
監事=小里 孝(株式会社十六銀行常務取締役)
玉木保裕(IAMAS副学長)
事務局=木下京子(フィラデルフィア美術館キュレーター)
 |
|
|
 |
永原 康史 |
1955年大阪生まれ | |