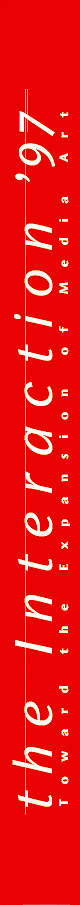
ナルシズムーフレスコ画からバーチャルリアリティへ
http://viswiz.gmd.de/IMF/liquid.html
 ナルシズムを社会の鏡に写したときナルシズムは自己投影、自己認識という姿になる。ナルシズムは自己保存のために必要であり(でなければどうして死者を魂として感じることができるだろう)、また一方で攻撃的な側面を持つ(愛するもののためには破滅をもいとわない)。
ナルシズムを社会の鏡に写したときナルシズムは自己投影、自己認識という姿になる。ナルシズムは自己保存のために必要であり(でなければどうして死者を魂として感じることができるだろう)、また一方で攻撃的な側面を持つ(愛するもののためには破滅をもいとわない)。
 ナルシズムをアートの鏡に写したとき、古くはポンペイのフレスコ壁画に自己愛の比喩としてあらわれる、神話の中のナルシスの姿が写し出される。オビッドの「メタモルフォーシス」では同一と相違、対立と融合を弁証法的概念を、エコーとナルシス自身の姿を写した水面を暗喩的に使って述べている。鏡は現実を裏返し、そこにありながら、ないものを見せ、存在と不在にかんする同様な問題を提起する。
ナルシズムをアートの鏡に写したとき、古くはポンペイのフレスコ壁画に自己愛の比喩としてあらわれる、神話の中のナルシスの姿が写し出される。オビッドの「メタモルフォーシス」では同一と相違、対立と融合を弁証法的概念を、エコーとナルシス自身の姿を写した水面を暗喩的に使って述べている。鏡は現実を裏返し、そこにありながら、ないものを見せ、存在と不在にかんする同様な問題を提起する。
以降1000年の間、ナルシスは美術作品のモチーフから姿を消し、ルネッサンスの時代になって再び取り上げられるようになる。カラバッジオの「ナルシソ」は水面に映った自分の姿に陶酔している青年を描いている。そこで使われた、対象となる人物や物体にいろいろな方向から光をあてる“スポット照明”は、現代においては映像や舞台芸術で用いられている。オスカー・ワイルドは「ドリアングレイの肖像」(1890)において自己破壊的な、自己愛の物語を描いている。若さと美を理想として求めるあまり、美しくはあるが、現実から遊離した人生を送る。アルバート・ルウィンの1945年の映画「ドリアングレイの肖像」では、絵画を映画の中心に据えている。映画の主人公は、自分と肖像画とを置き換えた。肖像画が年老いていく一方で、ドリアングレイ自身は、若いままでいるのである。
 「硬化する波」と「ナルシスの水鏡」では、メディアのナルシスたちにとって現実と非現実の境界はない。そこに見える虚像に触れた瞬間、もうひとつの世界へと入り込む。触覚は、仮想世界へのインタフェースであり、異なる言語、異なる感覚をつなぐ媒介者である。この作品は、人間ー機械ーコミュニケーションの新しい方法を提示する。水面に触れ水鏡がゆらめくことは現実と同じであり、機械とのインターフェイスを感じさせない。そうしたあたりまえのことを通じてこの作品はバーチャルリアリティとなるのである。
「硬化する波」と「ナルシスの水鏡」では、メディアのナルシスたちにとって現実と非現実の境界はない。そこに見える虚像に触れた瞬間、もうひとつの世界へと入り込む。触覚は、仮想世界へのインタフェースであり、異なる言語、異なる感覚をつなぐ媒介者である。この作品は、人間ー機械ーコミュニケーションの新しい方法を提示する。水面に触れ水鏡がゆらめくことは現実と同じであり、機械とのインターフェイスを感じさせない。そうしたあたりまえのことを通じてこの作品はバーチャルリアリティとなるのである。

ウルフガング・ストラウス(1951年生)は建築家であり、また、“仮想建築(Virtual Architecture)”や“インターフェース・デザイン”といった分野を手がけるメディア・アーティストでもある。フランスのコルビジェ研究センター内に“バーチャル・ワールド・スタジオ”を創設、アート+コムの設立メンバーのひとりで、現在はザールブルッケン美術学校(ドイツ)でインタラクティブメディアの客員教授、GMDメディアコミュニケーション研究所の客員研究員を勤める。「ベルリン-サイバーシティ」「リスポンシブ・ワークベンチ」「硬化する波」などの作品がある。
クリスチャン-A・ボーン(1963年生)はGMD研究所でコンピュータサイエンスを学び、並列コンピュータ(コネクション・マシン)上で動作するラジオシティ関連プロジェクトのリーダーである。GMDメディアコミュニケーション研究所ではニューラルネットワークを博士課程の研究課題としている。「リスポンシブ・ワークベンチ」、「空間ナビゲーター」のインターフェイスとして言葉やジェスチャーを使った自然なシステムを開発した。