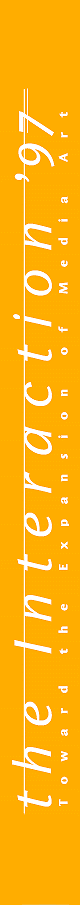
 ロッテルダムで開かれたISEA'96の展覧会に、世界中から集まった仮想領域の作品の中で、藤幡正樹の「ビヨンド・ページズ」という作品だけは、私にそこにずっといたいと思わせた作品だった。それは作品が、子供っぽい驚きをそそるからでもなく、上品な調和を持った古典主義的な仕上がりのせいでもない。それはインターフェースの向う側にあるときめくような世界と、こちら側の世界との境界で、喜びと作品形態の完全さと知性が融合していたからに他ならない。作品のページには、「リンゴ」や「石」などの自然の物体が、「ドア」や「電灯」のような人工物のかたわらに折り込まれている。それらの間には「書く」ということ、書物そのものにとって当然なこと、つまり自然を超越する、自然物ではない人間としての刻印が記されているのだ。
ロッテルダムで開かれたISEA'96の展覧会に、世界中から集まった仮想領域の作品の中で、藤幡正樹の「ビヨンド・ページズ」という作品だけは、私にそこにずっといたいと思わせた作品だった。それは作品が、子供っぽい驚きをそそるからでもなく、上品な調和を持った古典主義的な仕上がりのせいでもない。それはインターフェースの向う側にあるときめくような世界と、こちら側の世界との境界で、喜びと作品形態の完全さと知性が融合していたからに他ならない。作品のページには、「リンゴ」や「石」などの自然の物体が、「ドア」や「電灯」のような人工物のかたわらに折り込まれている。それらの間には「書く」ということ、書物そのものにとって当然なこと、つまり自然を超越する、自然物ではない人間としての刻印が記されているのだ。
実際の展示では、プロジェクターが革装の本のイメージをタブレット上に映し出し、ライトペン(実際にはスタイラスペン)で、「石」、「ドア」、「電灯」、「文字」などを次々に動かすことができる。
(中略)
 言語は、もともと人間から切り離されている自然と、人間が作りだしたものの間をつなぐものなのだ。「石」の奇妙さも「電灯」のスイッチの異様な感じも、この作品では言語によって親しめるものになってしまう。目の前の「リンゴ」に驚き、自分と関係のないのものを操作して喜ぶ、私たちはこの作品によって、見たこともないものを親しみあるものにすることができるのである。まるで、ライトペンによってイメージをうまく扱う子供が、ちょうつがいの不思議な動きに歓喜するように、私たちはそれを手に入れることができる。つまり、イメージのドアをスイングさせて開けさせているのは、言語が「てこ」の中心になっているからなのだ。マルチメディアの目標が、旧来の動画映像のまねごとをすることではなく、むしろ新しい文学を産むことであり、これらのすき間をつらぬく新しい言語の創造であることに、わたしたちは気付くのである。
言語は、もともと人間から切り離されている自然と、人間が作りだしたものの間をつなぐものなのだ。「石」の奇妙さも「電灯」のスイッチの異様な感じも、この作品では言語によって親しめるものになってしまう。目の前の「リンゴ」に驚き、自分と関係のないのものを操作して喜ぶ、私たちはこの作品によって、見たこともないものを親しみあるものにすることができるのである。まるで、ライトペンによってイメージをうまく扱う子供が、ちょうつがいの不思議な動きに歓喜するように、私たちはそれを手に入れることができる。つまり、イメージのドアをスイングさせて開けさせているのは、言語が「てこ」の中心になっているからなのだ。マルチメディアの目標が、旧来の動画映像のまねごとをすることではなく、むしろ新しい文学を産むことであり、これらのすき間をつらぬく新しい言語の創造であることに、わたしたちは気付くのである。
(ショーン・キュビット)
1956年、東京に生まれる。1981年、修士号を取得。1982年から84年、株)セディック。現在、慶応義塾大学環境情報学部助教授。l983年に「Mandala1983」で、ビデオ・カルチャー・カナダからCG部門大賞を、l996年に「Global InteriorProject#2」で、アルス・エレクトロニカから、インタラクティブ・アート部門、ゴールデン・ニカ賞を授賞。
主な展覧会として、
"脱着するリアリティ"(入江経一との共同制作)スパイラル・ガーデン(東京)1992
"生け捕られた速度" ICCギャラリー(東京)1994
"未来の本の未来"展(慶応大学湘南藤沢キャンパス)を企画 1995
"グローバル・インテリア・プロジェクト#1"インターコミュニケーション'95
(東京)1995
"グローバル・インテリア・プロジェクト#2"、"ビヨンド・ページズ" シーグ
ラフ・アートショウ(ニューオリンズ)、アルス・エレクトロニカ(リンツ)、DEAF(ロッテルダム) 1996
