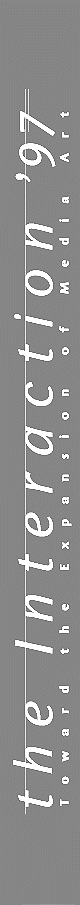
ひとりの男が座って本を読んでいる。部屋の中に入ると、あなたをちらりと見る。そして、また本を読み続ける。このあと部屋の中をどう動くかで、その男の反応が変わる。




この作品では、いくつかの単純な視覚的要素の組み合わせだけで、どのくらい複雑な対話、それも言葉のない対話ができるかを確かめてみたかった。この対話の鍵は、プライベートとパブリックな空間。もし彼のプライベートな空間を犯そうとすれば、彼はあるやりかたで反応をおこす。もし彼のプライベートな空間に敬意を払って行動すれば、彼はまた別な反応を示すだろう。ピエール・レボー(シアター・ウブの劇団でケベック州、ヨーロッパで有名な役者)が、全身を使って演技をする。険しい表情の表現からすばやい動きまで、時には好奇心に満ち、時にはふざけ、時にはおどしまで演じてみせる。
私は他の作品と同様に、コンピュータで、あたかも知性があるように見えるものをつくりだすことに興味がある。単純な規則にのっとり理路整然とした世界を構築することにより、知性のイリュージョンを創作することが出来る。なぜこのイリュージョンが成立しているのかを理解できれば、うまくいかなかったときにその問題点を暗示してくれるだろう。
30年前に初めてPDP-8で簡単な足し算のプログラムをつくらなければならなくなった時から、コンピュータに対して愛と憎悪というふたつの感情をもちつづけた。二度目にコンピュータに触れたのはそれから10年後のことである。それは写植屋でのことで、現在ウェブページでHTMLのタグを付けるように、フォーマット用のタグを埋め込むというものであった。それでもPDP-8での紙テープよりは一歩前進だ。それからさらに10年後、マッキントッシュのハイパーカードで遊びはじめたのだが、単純明快そのもの、大いに気に入った。はじめてコンピュータで「書いて」いる気分だった。
その最初と2番目の出会いの間の頃、フィルム制作をしたくなったが、それには膨大な資金と多くの人手が必要だ。80年代中頃にマッキントッシュを発見した時、映画のようなものを作れるのではないかと思った。そしてハイパーカードはそれを現実のものにした。
1987年から1994年までの間、私は一連のハイパーメディア作品、「グレン・グールド・プロフィール」、「メモリー・プロジェクト」、「オデッセイ」、「バ*ビーのヴァーチャル・プレイハウス」、を制作した。これらの作品はいずれもメディアに対する批判の要素を含んでいる。10年たって、ハイパーメディアはマルチメディアと呼ばれるようになり、ハリウッドのように今や膨大な資金と多くの労働力が必要とされている。
しかし、作品創りのためには最新で最高速のコンピュータやソフトウェアを使用しなければならない、という考え方には反対だ。そういったツールを使いこなせるようになるために十分に時間をさかない限りは、決して作品など作ることはできない。
アップグレードし続けるということは自分のものにするだけの時間がないということだ。それよりも、一つのツールをできるだけ長く使い続け、十分に深く知る決心をしなければならない。
コンピュータはすごい。今や至る所にある。コンピュータは私たちが自分自身を理解し、比較するためのメタファーとなった。しかしこれはメタファーにすぎない。人間の脳はコンピュータのようなものであるが、コンピュータではない。多くの人々がこの違いを忘れている。
1995年1月より私はモントリオールにある研究所でインターネット上の情報を視覚化し、より個人的なものに再構成する研究を始めた。1996年夏同研究所の閉鎖に伴い、メルツコム(Merz.Com,http://www.merzcom.com)という会社を作り、JAVAを使った、情報組織化ツールの商品化を行っている。
