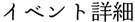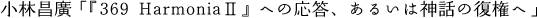「この作品(「369 HarmoniaⅡ」)は文化人類学者・中沢新一氏とのコラボレーションによって生まれ、中沢氏の提案に従い、人類学者クロード・レヴィ=ストロースが報告した南米神話に触発されて作曲されたものである」と、この「369 HarmoniaⅡ」についての「解説」が始められる。また(こちらの方がより重要であるが)、以下のような但し書きが添えられてもいる;「私は作品ごとに架空の『由来』をコンサート・プログラムに発表してきた。私にとってそれは作品の説明ではなく、音楽が成立するために必要な『作品の一部』である。そしてこの「369」の場合は、私ではなく中沢氏が書き下ろした『小説369』がその『由来』の位置を占めることになる」。
「由来」と称されるテキストそのものの作曲作品への引用ではなく、文字通りこの「由来」から〈作品〉が始まる、というのが三輪作品に一貫した姿勢である。多くの芸術作品は、何らかの「先行事例」や「参照作品」といった〈過去〉ないし〈契機〉をもち、それこそが作品の〈歴史性〉を支えている。ここで言う〈歴史性〉とは、作品が特定の表現ジャンル(三輪であれば現代音楽、あるいはより広大には音楽)において確固たる〈系譜〉を保証するような〈音楽史制作〉への積極的ないし消極的加担をさしている。ある場合には、それは権威づけになるだろうし、また別の場合には作家ないし作品理解のための手引きともなろう情報である。
三輪作品がきわめて人類学的な出自(由来)を前提として音楽作品がつくられていることは、そうした〈歴史性〉という文脈におさまらない特性をあらわしている。中沢新一が三輪をそそのかしたときに提案されたのが「裏ベリオをやりましょう」という一語であった。ルチアーノ・ベリオは、管弦楽曲『シンフォニア』(1968)の第一部において、レヴィ=ストロースの『神話論理Ⅰ 生のものと火を通したもの』からテキストを引用して八重唱部分としているのだが、ベリオはレヴィ=ストロースの本意を理解していない、というのが中沢の指摘(企み)であった。それに対して三輪は「もしベリオが何かを『理解していない』と言うならば、まさにその物語や感情を音楽によって表現するというロマン主義的(?)姿勢、つまりその時代性のことなのではないか?」と、とりあえずの「正解」を述べている。
上述した〈歴史性〉においては、一種の「系譜づくり」としての目的もあり、それ自身、ロマン主義的(?)な志向性を有しているとも言えるだろうが、ベリオにとってはレヴィ=ストロース自身も後年まで知ることのなかった「引用」のしかたであったことを思い起こすと、その八重唱は「引用」というよりも、楽曲『シンフォニア』の「歌詞パート」であった可能性も濃厚なのである(事実、他の部分においても、キング牧師の名前が素材として用いられていたり、マーラーの交響曲第二番の第三楽章を基調に多くの「先行作品」がコラージュされていたりする、という意味で多分に実験的かつロマン主義的作品なのである)。いったい「物語や感情を音楽によって表現する」というロマン主義的な態度とは何なのか、それが問われなければならないだろう。
また、三輪においてのテキストは過去の文学や映画などから取材されたものではなく、自身によって創作された〈由来〉であることは、「作品の一部」であると喝破する三輪の姿勢を少しも揺るがすものではなく、何よりも「過去」とか〈歴史性〉といったものが作品の前面に登場していないことは興味深い。しかし、五線譜に音符を乗せることや伝統的な楽器の使用、あるいはコンサートという形式の遵守といったごく歴史的な行ないは(三輪のことであるからもちろん多くの例外もあるけれども)、「音楽作品」であることの重要な立場表明であり、その必然性についてもまた問われなければならない。
必然性。ベリオにはレヴィ=ストロースの神話分析についてのテキストを「引用」する必然性がどこに存したであろうか。そのことに着目することは、ベリオの『シンフォニア』を理解するための必要な手だてであろうと思われるが、詳細は避ける。だが、レヴィ=ストロースのテキスト、すなわち「神話」と「音楽」とのつながりについて思いを馳せることは、ベリオ作品のみならず、多くの〈由来〉をわれわれの知らない「ある民族の神話的身ぶり」として創作しつづけた三輪作品を理解するためには、より重要なことなのである。そのことに関しては、まさに「369 HarmoniaⅡ」にとっての「参照作品」ともなる中沢の著作『虹の理論』(新潮文庫、1990)には、レヴィ=ストロースの書物に関して以下のような記述がなされている;「(『生のものと火を通したもの』の)冒頭には、フランスの作曲家エマニュエル・シャブリエが、友人の新築祝いにプレゼントした『音楽にささげる』という小さな楽曲の一部が引かれ、その上に大きな文字で『音楽にささげる』という献辞が印刷されてある。この本のなかで、レヴィ=ストロースは音楽と神話とが、人間の精神のなかのきわめて近い場所にいることをしめそうとし、そうするためにはありきたりの科学論文のスタイルをとったりしたら、神話のもつふるえるような息吹きを殺してしまうことになるので、神話の構造分析をテーマにする一冊の本の全体を、まるまる音楽の形式にしたがってつくってみるという大冒険をおこなったのだ。『半音階的作品』という一章はこの本の後半、川魚を捕るための毒の起源について語っている、たくさんの南米インディアンの神話の分析にあてられた部分に、登場してくる。『毒の起源の神話』とはいっても、どの神話の語り口も多彩で、そこには、動物と人間との結婚によって生まれた子供のエピソードや、川底に棲む巨大な『虹の蛇』の話や、鳥の鳴き声と羽根の色の違いがどうして発生したのかを語っている物語などが、じつにたくみにブレンドされて、読んでいるだけでどんどん吸い込まれていくような面白さをもって、語られているのである」。レヴィ=ストロースが壮大なシンフォニーを構築するように一冊のテキストを書き、またそこで引用されている「毒の起源の神話」も多くの断片的な神話があたかもひとつの「最初の物語」へと回収されるように集められ構成されており、それを中沢が『虹の理論』のなかで引用され、ワーグナーの『トリスタンとイゾルデ』へと導かれていく。
神話のような音楽、あるいは音楽のような神話。わが国においては記紀(『古事記』と『日本書紀』)のような「非-正統日本史」的な記録だけが「神話」と呼ばれ、それ以外の国内の各地に広まる伝承の類は柳田國男によって「民俗学」的資料のなかへアーカイヴされてしまった「わたしたちの物語」を、もしかしたら三輪は音楽によって復権させようとしているのかもしれない。
(小林昌廣)
小林昌廣(IAMAS教授、医療人類学、身体表現研究、芸術批評)
1959年東京生まれ。植物生化学の研究ののち、大阪大学大学院医学研究科博士課程満期退学。大学院では医療人類学、医学史、医学哲学などを勉強し、中国 を中心にした東南アジア諸国での非西洋近代医学のフィールド調査を行なうと同時に、日本独特の医療文化である「肩こり」「持病」「血の道」などについての 広域的研究を行なう。著書に『病い論の現在形』(青弓社)、『臨床する芸術学』(昭和堂)、『「医の知」の対話』(人文書院)など。京都造形芸術大学芸術 学部芸術表現・アートプロデュース学科教授、同大学舞台芸術研究センター主任研究員を経て、現在、情報科学芸術大学院大学教授 。