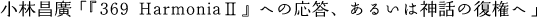小林昌廣

-世界の中心大垣で未来の文化を考える-
シリーズ:a.Laboからの応答 #4D
小林昌廣
神話的なるものの復権 “三輪眞弘『369 Harmonia Ⅱ』”への応答
レクチャー
前回のプレゼンテーションを担当した三輪眞弘への応答として、小林昌廣によるレクチャーが行われる。小林はいつものように、三輪作品を理解するための三つのキーワードを挙げることから始める。
1. 架空の物語、由来
2. ロマン主義
3. テクノロジー
三輪作品は、ほぼ確実に「という夢を見た」という言葉で終わる、ある夢についての文章が付される。それらの文章では、わたしたちの知らないある国の民族、部族における、身体的な身振りや宗教的な習慣、あるいは驚くべき奇跡的な動きなどが記されている。そうした夢、架空の物語が作品のモチーフになっており、さらにはそれが、そこから作品に入っていくための契機というだけではなく、音楽の冒頭、つまり作品の一部となっている。作品の由来となる、ヴァイオリンの演奏方法を二種類しか持たないという少数民族の物語を読むとき、もうすでに音楽は始まっている。
続いて小林はロマン主義について次のように述べる。音楽におけるロマン主義をごく簡単に説明すると、作曲家自身の感覚や感情を、音楽において表現するということになるが、それを拡げていくと、その作曲家自身が所属している時代、国家、文化などを音楽において表現していくような、いわゆるロマン主義的な態度、しばしばネガティブに受け取られているそうした態度として言うことができる。ロマン主義が一般化して以来、それを乗り越えていくかたちで、新しい考え方や指向性が要求、あるいは要請されるのが、ある意味で正統な音楽史の進み方と言えるのではないだろうか。
最後にテクノロジーであるが、3.11以後、人々はテクノロジーというものを、非常に危険視するようになった。あるいはほとんど信用しなくなってしまった。テクノロジーは、丁度ロマン主義と表裏一体を為すかたちで、今の芸術を表現するときには非常に重要な問題である。わたしたちは今、テクノロジーについて改めて考え直さなければならない何度目かの大きなポイントにあるのではないだろうか。三輪作品と現在を考えるとき、この三つ目のキーワードが非常に重要なものとなるだろう。
レヴィ=ストロースと音楽
クロード・レヴィ=ストロースは、神話についての著作『生のものと火を通したもの』(1964)の中で音楽について触れている。そこでは、神話についての考え方と、音楽についての考え方が非常によく似ている、あるいは一部重なっているということが繰り返し述べられる。目次を見ると、それは本というよりもむしろ音楽として考えられているかのようである。見出しに使われているのはすべて、何らかのかたちで、音楽作品においてしばしば用いられている表現である。第3部を例に取ると、以下のようになっている。
第3部
I 五感のフーガ
II オポッサムのカンタータ
a オポッサムの独唱/b ロンドー形式のアリア/c 第二の独唱/d フィナーレのアリア 火と水
本のタイトルの、「生のもの」は「自然」、「火を通したもの」は「文化」のメタファーとなっている。それぞれは、この本の中で音楽の芸術性を考えるときに持ち出される、音楽におけるふたつの格子、つまり座標軸にもなっている。一方は「生理的格子」であり、それはわたしたちの生理的に制約された身体や、または時間などについても言えるだろう。音楽は、そのような生理的格子によって作られているのだが、一方でレヴィ=ストロースは、音楽を聴いているとき自分は仮死状態にあり、心臓の鼓動は停止し、有機的、生理的な自分の身体を自覚する必要がないような状態が継続しているとも言っている。対してもう一方は「文化的格子」とされる。行事や儀礼など、文化におけるわたしたちの生活のさまざまな場面で使われる音楽は、時として生理的格子を超えなければならない。つまりそれを我慢しなければならない場面に出くわす。例として、小学生が意味の分からない退屈な歌を起立して聴かなければならないという場面が挙げられる。
レヴィ=ストロースは作曲家という一部の集団を高く評価している。そして、そのような曲を作って提供する側の人間と、それを聴取するのみの人間との間の、ある種の相互作用について、レヴィ=ストロースは「わからない」と言っている。そのことについて述べられた箇所で、まず音楽は、あるメッセージを伝達するための「言語活動」であるとされている。そのとき言語活動は、発声や動きなどの生理的限界、さらには二つの文化の間での受け止められ方の違いを伴う。言語であれば翻訳することができるが、音楽は翻訳できない。ある音楽を別の音楽に翻訳したり、あるいは絵画に、ダンスに翻訳したとしても、それらは別に表現したということに過ぎず、翻訳には当てはまらないだろう。レヴィ=ストロースによると、理解可能でありかつ翻訳不可能なのは音楽のみであり、それは神々に似た創作者によって、ひとつの謎を提出するかのように作られる。
神話―日本―民俗学―民俗資料
レヴィ=ストロースの「神話論理」では、アジアの神話がほとんど扱われていないが、こと日本においては、その場所性から神話自体が成立し難いものとなっている。日本の神話と言えば、古事記と日本書紀が思い出されるかもしれないが、それらは実は神話と呼びうるものであるかどうかは判断し難いものであるとされている。歴史解釈の世界では、それらは神話ではなく事実であり、正統な歴史の一部であるとされ、神話の専門家の中では、それはむしろまだ神話に至っていない物語の類であり、日本の民族の中で共有されてはいなかったと判断されている。あるいはそれは正統な神話ではなく、後になって作られた記録であるとされている。日本には古くから思想的に単一民族であるという強固なイデオロギーが存在していたため、複数の民族の間で神話を共有したり、それぞれの民族がそれぞれの神話を持つということが困難であった。そうしたことから、日本は正統な神話の成立しにくい場であると言えるだろう。
ここで小林は、最終的に三輪作品の「神話学」を抽出するにあたって、民族研究を大きな要素として持つ諸々の一般的な学問分野について確認していく。文化人類学(Cultural Anthropology)は、人間の生活を文化という観点から研究するという学問であるが、日本では元々民族学と呼ばれていたものであり、日本語において、そのふたつはほぼ同じものであると理解されている。民族学(Ethnology)は、西欧諸国の植民地政策に伴って成立したものであると考えられている。西欧は、その高踏的な立場から他の地域の文化習慣を捉え、それが民族学の起源となっている。民族誌学(Ethnography)は、民族学的な情報を図像や文字などで記録していくという、民族学の中でも特化されたジャンルである。
民俗学(Folklore)では、主として自国、自民族の文化にその関心が向けられる。柳田國男は、後に自らが「民俗学」として理解するものを、初期の頃は「口承伝承」あるいは「民間伝承」という言葉において表象していた。民俗学の資料は伝承であり、それは必ずしも図像や文字によって記録されたものでなくてもよく、伝えられているという事実が優先される。「民族学」は異民族、他民族の研究であり、対して「民俗学」のほうは、自民族、自国の人々の研究である。民俗学では、伝承されてきた現象の歴史的変遷を明らかにし、それを通じて現在の生活文化を相対的に説明するということが目指されている。
そのための資料を、柳田國男は『民間伝承論』(1934)において、三種類に分類して説明している。
1. 体碑...目に映ずる資料
2. 口碑...耳に聞こえる言語資料
3. 心碑...心意感覚に訴えて初めて理解できる資料
柳田が特に重視していたのは口碑であり、その初期には民話を編纂した『遠野物語』を発表している。三つ目の心碑とは、要するにフィーリングのことである。柳田自身も、この三つの区別では具体性に乏しく、特に心碑は恣意的にコントロールされてしまう危険性が伴うと感じており、この区分を発表した翌年に、再び三種類に整理した上で、その内訳を詳細に、より具体的に再定義した。さらに、柳田の弟子にあたる折口信夫は、民俗資料をさらに五種類に分類している。
1. 周期伝承(年中行事)
2. 階級伝承(老若制度、職業、性別による区別)
3. 造形伝承
4. 行動伝承(舞踊、演劇)
5. 言語伝承(諺、歌謡、伝説説話)
しかし、現在このような分類はあまり使われていないと小林は述べる。つまり、現在日本ではどこに行ってもネットワークを使うことができる。そのため、特別に民俗学的な関心の寄せられる地域というのは、ある意味でほとんどなくなっているのだということである。今現在、民俗学的な関心が向けられているのは、妖怪や都市、あるいは観光文化などであり、もはやかつてのように鄙びた地域に出かけていって、その地域のお年寄りから話を聞くことを手段とするようなものではなくなっている。
三輪神話学
三輪眞弘の作品では、様々なかたちで神話的な物語が書かれている。それを小林は「三輪神話学」と名付け、その骨法の抽出を試みる。まず、「という夢を見た」で終わる一連の神話は、三輪自身によって創作されたものであるため、それらは伝統的な民俗学の記述を超出していると言える。作曲家である三輪は、民俗学者や人類学者の学問的蓄積とはまた別の蓄積を持っている。そういうところから話を作っていくため、そうした専門家には到底作ることのできないような物語が展開される。世界中の民俗学者が集まったとしても、ヴァイオリンの奏法を二種類しか知らない民族などという発想が出てくることはおそらくないだろう。
次に、そこには特定の民族(人口などの具体的なデータはわからない)の身振り、つまり音楽の演奏方法やコミュニケーションの仕方などが描写されている。基本的には身振り手振りなどの記述によって身体性に濃厚に関わってくるような仕方で、それらの神話は構成されている。
さらに神話の中で音楽は、その民族の生活ないし祭祀の中から音楽的瞬間を紡ぎだすという仕方で表されている。すなわちその生活の中の音楽的な身振りを端的に抜き出すということではなく、元々その民族が持っている祭りや生活習慣などの中の音楽的な要素に言及するようなものとなっている。ヴァイオリンの奏法がふたつしかないというのは、物語の中でそのことのみが単独的に置かれているわけではなく、その記述の背後にある日常の生活、あるいは非日常としての祭祀、儀礼の存在によって包摂されていると言うことができる。
最後に、それらは当該民族の持つ固有のテクノロジーであると解釈されている。それぞれの民族がテクノロジーを用いて生活するのは言うまでもないが、この場合のテクノロジーとは、科学技術には翻訳できないようなものである。ここで小林は再びレヴィ=ストロースを登場させ、その著書『野生の思考』の中で「ブリコラージュ」と呼ばれているのものについて言及する。ブリコラージュとは、様々な民族において、それぞれの昔の知識や、外から持ち込まれたいろいろな技術を断片的に集積し、あたかも自分たちが元々持っていたかのような技術にしていくということであり、そうした方法は科学技術とは異なる、その地域やその民族、共同体の中で独自に成立するサイエンス、つまりは「野生の思考」であると述べる。さらには、三輪作品が、その由来として作られた物語の中に描写される民族において、自分たちの生活、文化、あるいは宗教的な営みなどを活性化させるために利用されているのではないだろうか(自民族を活性化させるための音楽)という意味において、音楽は固有のテクノロジーとなっていると結論される。
以上、「三輪神話学」とされるものの四つの観点が提出され、レクチャーは終了する。
ディスカッション
どうしても由来を作らないと気が済まない
安藤泰彦:作曲する段階と、物語を作る段階とは、どちらが先なのか。交互に合わさって同時進行していくのか、そのあたりの事情を聞きたい。
三輪眞弘:由来は後からできるということが大前提としてある。コンピューターの中で抽象的なシステムを作るのだが、それは人間によって演奏されるものとして作っているので、実際にそこに立ち会うとき、自分にとって最も納得できるのはどのような由来なのだろうかということを考える。『またりさま』の話は、最初は「夢落ち」の話にはしていなかった。そのため、「またりの谷ってどこにあるんですか」とまじめに聞いてくる人がいて、「イヒヒ」と思ったりもしたが、自分がやりたいのはそうした悪い冗談のようなことなのかということを随分長い間自問していた。自分の中ではっきりしているのは、どうしても作らないと気が済まないという衝動。いわゆるアルゴリズミックな全く抽象的な構造によって作られた音楽を人間が演奏するとき、そこに物語がなければ鑑賞者はそれをどう見ていいか分からず、それでも何らかのかたちで見ようとするとき、ある意味で鑑賞者自らが物語を作ってしまうということになる。それに対して私自身が先取りして由来を作り、その由来を作品と一致させたいということが、由来を作りたくなる衝動についての自分なりの分析だ。由来を作品の一部だと言っているように、「我ながらよくできている」とか「泣けてくる」というところまで自分が納得できる話を作ってきた。話ができると、今度は人間が演奏するとき、例えばカスタネットを持って前の人を叩くというとき、人間はそれを非常に機械的に叩いたり、あるいは宇宙まで響き渡るように叩いたりと、如何様に叩くことも可能であるが、そのとき物語は、そうした「どのように叩くか」ということを判断するための拠り所となる。つまり物語を手掛かりとして、「この物語だったら、こういうふうに叩くのは間違いだろう」とか「ふさわしいだろう」ということが生じる。
安藤:作曲のアルゴリズムがあって、演奏による曲の現実化があって、その間に由来としての物語があるという構造。ふたつの規則によって作品が二重になっているような感じがする。聴く人に対して由来が作用するということを念頭に置いている?
三輪:由来には必ず「夢を見た」と書くようにした。悪い冗談をやりたいわけではない、虚構を実際の話として理解させたいわけではない。そしてそれが虚構であっても夢であっても、ひとたび物語を読めば、その影響なしには作品を見ることができないということを確信している。それが作曲家の見た夢でしかないということを頭ではわかっていても、人はそういうふうに見てしまう、見ざるを得ない。
何らかの説明をしておくことで、他の説明をさせない
小林昌廣:ひとつの空想をあえて創作した(「という夢を見た」)と言うことで強調するのは、神話の再神話化的な作業だと言える。そこで聴き手はその物語において作品に接することとなるが、そのように物語の呪縛から逃れられないまま音楽に臨むというのは、極めてロマン主義的なスタイルと言えなくはないだろうか。
三輪:例えば若者が八人、鈴とカスタネットを持って何かしてても、見ている側はどう理解していいか分からないだろう。由来を置くもうひとつの意味は、そのような表れに対して何らかの説明をしておくことで、それは、他の説明をさせないということでもある。『またりさま』などで、人間が演算子となって練習を続けると、人間は案外簡単にトランスしてしまうものであることを経験した。そのときにもし、何か怪しい宗教のような変なものが入ってくると、すべてが壊れてしまう。もしこれを本当に宗教っぽくすれば、実際にそうなってしまうだろうということを感じたことが何度もある。私は純粋な音楽作品を創りたいだけなので、誰かがその行為を変な宗教のようなものとして見ようとする前に、説明を先取りしておく必要がある。
安藤:逆に、「数学的な法則性によって作られた」というある種の物語もあるが、そちらの方に走らせないようにという欲望もきっとあるのだろう。
三輪:音楽作品として社会に登録するためには、私にとってこの由来がどうしても必要だ。なぜならそれがコンピューターなどで作られたものである以上、それ以前の伝統的文脈がない純粋培養のようなものとしてあるため、それに対して物語ははじめからないと言っていい。あるとすれば、確かに「これは論理的な演算で作られている」と言うことは可能だが、それは音楽作品の説明にはならないと思う。ただし、架空の由来物語の中で説明している音楽的な内容、システムや演奏技法に関してはすべて正確に書いている。
安藤:由来についてもう少しだけ聞くが、三輪さんの作ったツダ族の話と、中沢さんの小説『369』とはどのような関係なのか。小説ができてから作ったのか。
三輪:小説が完成するのは、自分の作品が完成するのと同じくらいの時期だった。「369」という名前からして中沢さんの提案で、レヴィ=ストロースとの関係、物語との関係、そうしたことに関してはすべて中沢さんから材料が出揃っていて、それを基に私は音楽を書き、彼は小説を書いたという関係だ。
安藤:今回の場合は、作曲のあとに作られる由来と、作曲前の由来(出揃っていた材料)の二種類あるということ。
三輪:そういうことになる。技法に関しては、『虹の技法』という小品で今回の技法を実験していて、それは『369』の準備にあたるようなものだった。そういう意味では完全につながっていて、この作品は、南米の神話などの材料が予め与えられた状態でスタートしたと言える。
私が主であるわけにはいかない
前田真二郎:三輪さんは作品を発表するとき、プログラムノートというものに架空の物語を載せているわけだが、実際それが現代音楽というフィールドで、どのような受け止められ方をしているのか。現代音楽を含めた二十世紀の前衛芸術には、近代をいかに乗り越えるかというテーマがあった。美術系の人であれば、三輪さんの作品は、非常に分かりやすいかたちで近代的発想では決して生まれない音楽を、奏でられる音楽と物語をセットにして提示されていると解釈するのが一般的だと思うが、それが現代音楽の世界ではどう受け止められているのか。
三輪:プログラムノートに由来を書くということについては、普通に冷たくあしらわれるだけだ。ある賞の審査員は、私の作品の由来を本当の話だと思っていたくらいで、ある意図を込めてそういうことをやっているということに対しては誰も関心がないという状況だ。プログラムノートとは一体どういうもので、どういう機能を持っているのかということについてまじめに考えた人が、この日本では今まで誰一人としていなかったということだと思う。通常、作曲家のプログラムノートには、「作曲の経緯」を除いてふたつのタイプと、その混合形しかない。ひとつは、批評家を先取りして自分の作品を分析し解説するというもの、もうひとつは、その作品に対する思弁的、感性的、精神的な「思い」を叙情的にまとめたもの。
前田:アンチロマン主義を感じさせる発言がある中で、非常にロマン主義的な印象を受ける。
三輪:作曲家の思想とか世界観とか感性とか、そうしたものをなんとか音響化しようとすることがロマン主義では重んじられている。そこから、作曲家にはすばらしい感性がなくてはならないという考え方が出てくるが、その部分を私は拒否したい。結局のところ、西洋音楽はそのようなロマン主義的な方向には進まず、調性のない、リズムもわからないような難解な方向へと進んでいった。ロマン主義を引き継いだのはポップスであり、「私の中のこの熱い気持ちを君に届けたい」という、ロマン主義の名残みたいなものがテクノロジーによって受け継がれたものだと私は理解している。自分の思想や感性を音響化するということを私はしないため、私は何かに従うしかない、私を従わせるものがなければならない。つまり私が主(あるじ)であるわけにはいかない。そこで自分が従うべきアルゴリズムがあり、それにすべて従ってみせるのが自分の仕事だ。ではなぜそこまでアルゴリズムに拘束されなければならないのかと言うなら、そこからは神秘主義とかロマン主義といった話になっていくのかもしれない。
小林:架空の物語だけが音楽を語るためのひとつの力(手掛かり)となっているとすると、そのとき物語はロマン主義的なものを突破する。つまり、物語は音楽を包んでしまい、そうすると物語は音楽を説明するものではなく、それ自体が音楽になる。
三輪:今日紹介されたレヴィ=ストロースの語る作曲家というのは、すごく近代的なロマン主義的だと感じる。音楽作品の前において、作曲家が本当に神様になってしまう。自分はそうではあり得ないと感じている。
前田:今回の作品が大阪で初演されたとき、私は現場で聴いたのだが、やはり現場のほうが、録音されたものを聴くよりも感動があった。もともと劇場は、何かしら作曲者や演奏者が発見したものを提示し、それに立ち会う人がいる空間として近代に成立したものだと思うが、そうした「演奏の場」のようなところを三輪さんは非常に大事にしているのではないだろうか。複製されたものにあふれている時代において、そのような「演奏の場」のようなものをもう一度復権したいという方向性が感じられる。
三輪:初演ではあえてコンサートホールではなく倉庫のようなところに特設ステージを作って、どこが正面というわけではなく、お客さんにはステージの周囲に座ってもらった。基本的にはそうした面においても、伝統的な西洋音楽のフォーマットから自由になりたいと思っている。そういう意味では、ステレオ装置で聴いてもらったのは、ある種妥協していると理解してもらってもいいのだが、ただし皆が一緒に聴くということについては私は非常にポジティブに考えていて、さらに生演奏の体験に近付くひとつの形態なのだろうと感じている。
ふたつの性格が異なるレベルで現れている
安藤:記録映像を使わなかった理由は?
三輪:事実としては撮影していなかったと思うが、もし撮っていたとしても、それを見てもらうことはしなかっただろう。記録映像よりは、録楽(生演奏ではなく、録音された音楽)のほうがいい。映像と録楽はいずれも記号であるが、例えばアイドルの映像をスマートフォンで見ても、街角の巨大なスクリーンで見ても、そのどちらにもアイドルの存在を感じることができる。大きさが等身大とはかけ離れていてもそう感じられるのは、それが記号だからだ。ある意味ではそれは縮尺の違う地図のようなもの、すなわち地図は縮尺を変えても何も問題なく、最も都合のいい縮尺を選べばいい。録楽の場合、それももちろん記号なのだが、地図で言うと、一対一の地図に近い、あるいは記号であるということを見失いかねないようなものだと私は思っている。そこに映像が加わるとその関係性が変わってしまう。
質問者1:ロマン主義については、明快に違うと思う。むしろその対極であるフォルマリズム、あるいはラショナリズムだと思う。それとは別に質問だが、例えば素晴らしい建築を見に行ったとき、記号で得られたものを超えるような圧倒的な体験が得られるという場合があるが、三輪さんの作品においての、実際の演奏の持つある種の逸脱要素についてはどのように考えているのか。
三輪:まさに逸脱するからこそやめられないということが言える。やはり特別な演奏というのは、どこからくるのか分からないが、書いてある通りにやるのではない、何か違う次元がおそらく含まれている。現代音楽では、ある意味で音楽の本質や構造に関係のない、演奏に関係するような情報がどんどん細かく書き込まれていくようになっているが、それをやればやるほど、演奏する人間は楽譜を音にする機械のようなものでしかなくなるし、それしか許されないものになってしまう。この弦楽六重奏は、現在のそうした状況に対しての真っ向からのアンチテーゼだと考えている。というのは、楽譜は簡単で如何様にも弾くことができる。そのときに由来が生きてきて、当時の人ならばどのように弾いただろうと想像する余地や解釈する余地がそこに見出されるのだが、演奏家が賢明で技術がある場合には、前回聴いてもらったような演奏さえあり得るのだということを私は逆に知らされたという意味で、大きな驚きだった。
安藤:三輪作品の中には、フォルマリズム、ラショナリズム的な作曲家と、ものすごくロマン主義的な、今回も非常に高い密度の音、演奏家のバイブレーションがあって、それを上空から見ている三輪さん、そういう設定をしている三輪さんがいる。そちらのほうがロマンチックな気がした。だから、一人の作曲家がどちらかということを分けることはなかなかできない。何かふたつの性格が異なるレベルで現れている、それが三輪さんなのではないだろうかという印象を持った。
++++++
8回にわたって開催されたシリーズ「a.Laboからの応答」は今回が最終回となり、次回からはa.Laboによる新たな試みが開始される。日時は、2012年9月27日(木)18時30分より。
(佐原浩一郎/IAMAS 研究生)
三輪眞弘