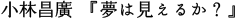前林明次
小林昌廣
三輪眞弘
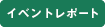
前田真二郎
-世界の中心大垣で未来の文化を考える-
シリーズ:a.Laboからの応答 #2D
小林昌廣
夢は見えるか?
レクチャー
前回の前林明次によるプレゼンテーション、〈『Container For Dreaming』―「夢見」が結ぶ人と場所〉への応答として、小林昌廣によるレクチャーが始まる。
まず三つのキーワードが提出される。
・都市
・臨場感
・通路
それらは前林から提出された三つのキーワード、
・stow away
・代償的内側性
・dreaming
と一対一で対応しているわけではなく、それぞれが複数の組み合わせによって結びついている。「臨場感」には、それを感覚する身体が当然のように前提とされているだけではなく、現実的に居合わせている空間とは異なる空間にいるような感覚という意味で、別の場所が前提とされている。そしてここでの「通路」とは、いろいろな場所を経由し、つなげていくパイプのようなイメージであると述べられる。アボリジニにおける「dreaming」が神話世界と人間をつなげる手段であるとすれば、そこにはわたしたちが生きている時代とは異なる時間、空間、人々とつながることを可能とする通路が走っている。
「通路」としてのコンテナ
「stow away」、潜行、「別の場所」への。コンテナはそのための通路となる。『Container For Dreaming』の体験者はこの通路(箱)の内部で、再生される「新宿のような」音と、外部から漏れ入ってくる実際の歌舞伎町の音という、いわば複数の外部の音を一挙に聴くこととなる。臨んでいる場所が混ざり合い、その体験は臨場感とはズレたものとなるだろう。前林は「夢見」という語について、諸々の知覚のズレを、身体で統合、再現するという意味として用いた。そのような意味において、コンテナは夢の「容器」として機能している。
歌舞伎町だけではなく、都市とは基本的に三つの要素が一体化したものとしてある。
・都市
・劇場
・悪場所
諸制度あるいは工学的技術によって都市空間の設計がなされる。そこには必ず制度的に劇場が置かれ、その周辺、そして隙間から必ず悪場所が生じる。前回前林によって紹介されたドゥボールの『スペクタクルの社会』が先駆となったと言われているパリ五月革命においては、学生によって国立劇場であるオデオン座が占拠された。革命が起こる場所であるということを考えると、劇場もまた悪場所なのかもしれない。いずれにしても都市には劇場や悪場所が付随しており、そこに出かけていく人にとっての非日常と、そこに暮らす人にとっての日常とが通じ合いながら存在している。そしてそのような場に突如としてコンテナが出現する。
ここで、コンテナが登場する最も新しい映画のひとつ、アキ・カウリスマキ監督作品『ル・アーヴルの靴みがき』が紹介される。物語の中で、密航者らの入ったコンテナが発見される。コンテナ密航には死の危険が大きく付きまとっている。つまり密航者とは命懸けで未来を夢見る者たちである。アフリカからル・アーヴルまで運ばれてきた少年は、コンテナの外に出ることによって自らとアフリカを切り離し、初老の男の世話になる。そこから自分の未来への次の通路を探していく、そのような映画であると言うことができるのではないだろうか。
場所からの解放
「代償的内側性」とは、小説やテレビ番組など、メディアを通じて作られる場所の経験である。まず、9.11が映画的な場面として解釈されたという例が挙げられる。その価値評価は別として、わたしたちはそういうふうに解釈してしまうのである。実際に起こったことを現実に把握できないような場面に立ち会うとき、わたしたちは映像体験などのフィルターを通してそれを再解釈するように習慣化されてしまっている。出来事の現実的性質を取り払い(脱埋込)、別の情報に置き換える(再埋込)。このような意味において「代償的内側性」という語を扱うとき、そこには「表象」という語を与えることが可能となる。表象とは、情緒や感覚についての、別のもの(身振り、言語、あるいは芸術表現)による表出である。現実の場所と、メディアによって表象された場所との間には、その場所の解釈において、錯覚、誤読、混濁、ズレを含んでいる。
続いて小林はエドワード・レルフを参照し、「代償的内側性」を、他の場所性(場所の同一性)との関係において説明する。「外側性」とは、自らと場所との関係の脆弱性を指す。「感情移入的内側性」は読んで字のごとし。「実存的内側性」とは、場所との無意識的な関わりであり、無意識的な関わりが断たれた場合、その場所は「実存的外側性」を帯びたものとなる。この場合、場所を身体と読み替えると、理解がより実感的に得られるだろう。自分の身体への無意識的な関わり、もしくは麻痺したり骨折したりした部位からの疎外。レルフの『場所の現象学』では、そうしたいくつかの場所性の中に「代償的内側性」が位置づけられている。それは小説やその他の媒体を通じた事後的な場所の経験、つまりは追体験である。
『Container For Dreaming』は場所からの解放を目論む。コンテナの中で新たな代償的内側性が埋め込まれる。歌舞伎町を別の場所としてイメージすること、あるいはどこでもない場所として。
現在の歌舞伎町は、戦後の復興において、鈴木喜兵衛と石川栄耀という二人の人物を中心として構想され、実現された都市計画を下敷きとしている。当初の構想は「東向きに芸能施設をなし、道義的繁華街を建設する」というものであり、誰もが楽しめる繁華街が目指されていた。しかし現在は必ずしも構想通りであるとは言い難いものとなっている。都市とは、彼らが考えるような理想のままにできあがるのではなく、隙間、空所、ちょっとした通路があれば、そういうところに続々と悪場所の分子がはびこり、その場所を悪場所化していくのだが、それが都市のあり方として非常に魅力的な部分であると言えるのではないだろうか。
「夢見」の空間―夢を見ることの断念
前林作品においての「dreaming」は、「目を閉じ、眼前にはない事物、場所について心を働かせること」であった。小林は、そのような定義を「meditation(瞑想)」に結びつけて語る。「meditation」では、自分の身体をメディアとして、超越的な異なる世界へと行き来する。様々な記号が通路としての身体を出入りするが、記号のひとつの集積体のようなものをここでは「夢」であると考えたい。フロイトによると、「夢には、どこか余所から来たかのような得体の知れない性質がある」。夢は非現実であると同時に、現実とつながっている。夢は現実ではなく夢であるが、それと同時に夢は現実の断片、あるいは変形された現実を素材としている。
日本語で「夢を見る」と表現されている語を英語に訳すと「dream」となる。watch a dream や、look at a dream などは自然な表現ではなく、仮に日本で採用されている「見る」という動詞を用いずに「dream」を翻訳するとなると、「夢す」となるだろう。現実には目に見えているわけではない夢を、人間の身体が映像として捉えるのは、認識において最も比重の高い感覚、すなわち視覚を拠り所としようとするからである。人間は、夢というものを「見よう」と、急速に眼球を動かして(レム睡眠)、脳の中の世界を視覚化しようとしている。眼球を動かすことによって視覚化しようとしているのであって、脳の中に視覚化された世界が映っているわけではなく、夢は見ることができない。夢を見ようとして断念させられているところ。「夢見」の空間が生まれるのは、身体がそのように作用する場なのである。
夢と同様に、「暗黙知」もまた意識に上ることのない身体の作動である。そうした身体的能力は、期せずしてわたしたちに贈与されている。
「臨場感」の同義語には「現実味」や「真実味」など、ある種の味覚、「眼前性」=視覚、あるいは触覚的な「没入感」、「一体感」など、様々に五感がちりばめられている。臨場感とはつまり、身体そのものが別のある世界に投げ込まれている感覚である。それはおそらく密航、潜行的な感覚であり、作品と作品の外部の世界とを連絡することに対してリアリティを与える。
どこまでが作品か
最後に小林は、いくつかの残された問題を提示する。
・個人と共同体の問題
歌舞伎町の住人と自治体としての歌舞伎町。作品の鑑賞者、作者、イベントのプロデューサー、場所の提供者。それぞれの関係。
・連続性と不連続性の問題
前林作品は、どこまでが作品か。コンテナを出て、新宿駅へ降りていくところまでは作品としての賞味期限、作品の温もりなどが残されているのか。美術館内の作品とは異なり、街と直接に関わるようなインスタレーションにおいての重要な問題である。
・感覚の問題
知覚やイメージの問題。
・記憶、体験、場所の問題
コンテナの中で聴いた諸々の音は、個人の記憶として埋没するのか、それとも記憶の中に抽象的な歌舞伎町のイメージを保存するのか。記憶がどこで発生し、どこで温存されるのか、大変興味深い問題である。記憶と合わせて、体験の問題、場所の問題、それぞれは読み合わせが可能な三つ巴となっている。これらはアートの創造における非常に大きな問題である。
・芸術と社会の問題
本活動a.Laboにおいて主題として扱われるべき問題である。歌舞伎町という特殊な社会を折り拡げていくことで、日本あるいは世界と芸術がどのように前述した問題とつながっていくのか。『Container For Dreaming』は、わたしたちの内にそうした問いを提起する可能性をもたらしている。
ディスカッション
眠る⇄眠らない / 「移動」と「空」の感覚
前林明次:自分の身体がメディアであるというひとつの例を挙げたい。テレビやラジオを付けっぱなしでそのまま眠ってしまうとき、番組で話されている内容が、夢うつつのイメージの中に出てくることがある。それが常々おもしろいと思っていた。意識的な力が弱まるときに、感覚されているものの状態が移行していくような経験。それもひとつの「夢見」の現象として考えることができる。
三輪眞弘:この作品は意識のある状態で体験してほしいのか、眠ってほしいのか、それとも眠りに入る瞬間が重要なのか。
前林:厳密に眠りに入って夢を見るということを義務づけているわけではない。15分という時間の中で体験者に与えられているのは、非常にシンプルな設定だ。「コンテナの中で寝て音を聴きながら何か変な感じがした」。体験者からそれを聞いた人が、その情報(設定)を歌舞伎町のイメージとつなぎあわせることでイマジネーションを生み出し、作品を体験してみたいという気持ちが起こるということもまた重要だった。
安藤泰彦:作品を体験しているとき、わたしは半覚醒状態だった。意識ははっきりしているが、仰向けになって寝るので、身体は脱力しており、音による様々な場所のイメージ、さらには時刻までもが混ざり合ってきて、かなり夢に近い状態だった。そのような作品体験の中に、「移動」の感覚があったように思われる。音の移動、継起的な変化によって、寝た状態のままどこかへ連れ去られる、あるいは移動するという感覚があった。『Sonic Interface』の場合、実際に現場を歩くわけだが、リアルタイムに変形された外部の音を聴くという体験は、夢遊病的な体験であると言える。そこでは場所からの疎外、そこにいながらも、いないような感覚を伴う。その場所性は、代償的内側性のみによって説明されるようなものではなく、様々に入り組んでいる。
前林:音を録るとき、マイクを低めに設定したので、街で寝ていたり、座っている人が聴いているものに近い聴こえ方をする。特に通路など、人が通るところでは、地面に近いところにマイクを設定することで、移動している感覚がより伝わるのではないかと考えている。
安藤:仰向けになって寝ながら音を聴くので、次第に空が意識されるようになる。普段、歩行時には空を気にすることはないが、コンテナから出ると空が気になってしまうという体験があった。
前田真二郎:寝ているか寝ていないかという境界を体験できる作品だった。歌舞伎町に到着する時点で疲労感を覚え、とても気持ちのいいベッドに横たわることで眠気を覚えるのだが、体験者は眠りにきたわけではなく、作品を鑑賞しにきたわけなので、起きていようとする。そして、そこで眠ってしまっても成立する作品であると解釈している。
前林:眠ったかもしれない、という人が多かった。はじめのうちは音に集中していたり、いろいろなことを考えながら作品に接していると思われるが、最後の2、3分になると、徐々にそうした意識が弱まってくる。最低でも15分の時間が必要だったのは、そのような状態を意図していたためである。
「聴こえてしまう」高精度の立体音響
前田:音のリアリティは作品を成立させる上で重要な点だと思うが、聴く側においては、例えば海の音を聴く場合、その音が本物なのかそうでないのかということが問われる。精度の高さへのこだわり、臨場感ということについて聞きたい。
前林:精度の高い立体音響は、実際の音に対してそれを疑って聴くかどうかの違いしかなく、ほとんど本物と変わりがない。ここで大事なのは、どのようにして身体的な反応を引き出すかということ。技術の精度が高まり、それと平行して、聴こえている音を本物として感覚する人間の側の精度も引き上げられている。そうした意味において、高精度の立体音響こそが、意識を飛び越えて直接的に身体へと到達する、到達してしまう。それは聴覚だけではなく、触覚的にも視覚的にも感じられる。そういう意味では非現実的だが、再生された音ならではのリアリティがあるという意味で特殊なもの。情報量の多さによって、意識というよりは、むしろ身体に届いてしまう。高精度の立体音響におけるそのような力を使いながら、こことは違う場所を重ねたり、空間を移動するということを試みている。
前田:はじめがあって終わりがあるタイムベースドの作品であるが、時間はどのようにして設定しているのか。
前林:『Sonic Interface』に関しては、ルートとの関わりがあり、場所に応じてどのような音の変化がふさわしいかということを考える。『Container For Dreaming』、『メトロノームと無響室のための作品』では、意識においてというよりは、身体の反応として「聴こえてしまう」ということを優先させ、聴いている側は、身体に届いた上でそれを疑ったり、本当なのかを確かめようとするということが起こる。そうした体験を全体としてガイドしていくために、ある程度のまとまった時間が必要となる。
都市の「隙間」が残り続ければいい
安藤:作品において歌舞伎町が必然であるとすると、その特性を音としてどのように表出しようとしたのか。
前林:歌舞伎町アートサイトは、シネシティ広場と大久保公園にコンテナが設置されているという枠組みがまずあって、ディレクターと話を進める中で、自らの作品プランはシネシティ広場の真ん中になければ成立しないということで結論が出た。歌舞伎町という場所性がこのような設定を可能にしたのだと言える。音は「新宿のような」音であり、それぞれの体験者のイメージや記憶に依存しながら、音と場所の関係性を感じてもらう。個々人において共通しているかもしれない「猥雑」なイメージを持つ歌舞伎町という場所にコンテナを置き、その中で音を聴くという設定は、歌舞伎町でなければ機能しないと考えられる。
安藤:大久保公園は非常にクリーンな空間で、鉄格子などで簡単に人が入れないようなある種のコンテナとしての空間性を持っており、その中に実際のコンテナが置かれていた。企画に対して思うことは?
前林:大久保公園は排除的な公園であり、そこにおかれたコンテナは二重のバリアを持つことになる。シネシティ広場にも排除が見られるが、排除しきれていないノイズ的な部分が垣間見える。
三輪:作者本人はそれらを排除すべきだと考えているのか?ホームレスがいるような場所でアートフェスティバルを開催するということについて、どのように考えているのか?
前林:あの場所をアートに対して解放しようという、企画自体の試みは、基本的に排除を目指したものだ。しかしそれでもあの場所には排除しきれなさというものがある。そこに自分の作品の可能性があると考えた。そしてあの場所もすぐになくなってしまうという予感がする。そういう意味では力が拮抗している状態のところに、あのような体験を設定することができて、作品的にはよかったと考えている。70年代初頭のニューヨークにおけるアーティストらの動きには、その条件としての「隙間」が存在していた。「隙間」はアートが何かを始めるときの絶対的条件であり、そういうものが残り続ければいいと思う。このような作品はもちろん場所に依存しながら成立しているが、最終的には場所との関係を創造していく身体的、意識的な作用が重要になる。その機能を存分に働かせるというところから、今後どういう場所、環境が必要なのかということを考えていくきっかけとしたい。
小林昌廣:ホームレスは都市部でなければあり得ない。ホームレスの存在には社会的、政治的な諸問題が絡んでくるが、総称すれば「場所」の問題に還元される。引き続き場所の問題は様々な方向から、芸術と社会の問題のひとつの有効な事例となるだろう。
場所との関係性を再構築する
質問者1:別の場所を使って連作化すれば、それぞれの場所の個性を浮き上がらせることができるかもしれないと思ったが、『Container For Dreaming』のプロセスは歌舞伎町だからこそ可能になったものなのか?
前林:自分がその場所に意味を見出せるかどうかのほうが、作品の形態などの要素よりも優先される。同じことをしても場所が異なれば、全く別の関わり方が必要になる。場所を感覚し、解釈し、そうして得られた場所性をどのように作品化するかということは、別のプロセスになるような気がする。ただ、こうした形態が歌舞伎町において生み出され、その可能性が開けていくのだとすると、それは歌舞伎町の力であると考えられる。前田真二郎『BETWEEN YESTERDAY & TOMORROW』において、福島に行って映像を録る人が比較的多かったのは、ひとつは場所との関係性を再構築しようとしていたのではないだろうか。そこには「自分の身体」と「映像メディア」と「場所」という要素をどのようにしてひとつのものとしてまとめられるかという感性があるように感じた。そうした関係の捉え直し、再構築というところに、作品のひとつの可能性があるのではないだろうか。
三輪:前林作品には視覚表現で言うところのミクストリアリティあるいはオーギュメンテッドリアリティ的側面を持っている。リアルな場所があり、その上にヴァーチュアルなものが入ってくる。そういう意味で違う場所になると、根本的に考え直さなければならなくなる。
前林:『Container For Dreaming』は作品の形態としては今までのものと似ているのだが、場所との関係性というところで、自分にとっては新しい、今までになかった展開だった。
質問者2:サウンドスケープの可能性を見出そうとしているのか、それとも音楽を内省的に捉え直したいのか。
前林:音楽として扱っているわけではない。環境音の再生音はダイレクトであり、抽象的に音の運動として聴くというよりは、聴こえてしまう、身体が反応してしまうという体験だ。そのために現実と間違えるような水準の音を再生する必要がある。身体的な作用を使いながら、別の空間(想像的にも、音的にも)に想いを巡らせる体験のための素材として使っていた。再生音と漏れ入ってくる外の音が混ざったり混ざらなかったりという変化の中で錯覚を引き起こし、その後に街を歩くときにそうした余韻が感じられれば、作品としてはおもしろい効果が得られると思う。
++++++
次回の安藤泰彦によるプレゼンテーションが予告され、第2回目のディスカッション・デーは終了。次回a.Labo、第3回目のプレゼンテーション・デーは6月28日(木)18時30分より。
(佐原浩一郎/IAMAS 研究生)