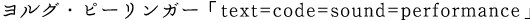ヨルグ・ピーリンガー

-世界の中心大垣で未来の文化を考える-
a.Labo 特別イベント
ヨルグ・ピーリンガー(アーティスト)
text=code=sound=performance
a.Labo 特別イベント、今回は東京のアサヒ・アートスクエアで開催された「東京国際音響詩フェスティヴァル」のために来日したオーストリアのアーティスト、ヨルグ・ピーリンガーが、(プログラミング言語を含む)言葉と音響、そしてパフォーマンスを融合したユニークで多様な活動について、歴史的、技術的、文化的な背景とともに語った。なお、通訳は本校の元講師、ジャン=マルク・ペルティエによる。
idea
アート作品をつくるアーティストであると同時に、詩をつくる詩人、音楽や楽器をつくる音楽家でもあるピーリンガーは、自身を表す最も適切な表現はメディアアーティストであると考える。さらに、ピーリンガーはコンピュータ学者でもあり、修士研究の内容はコンピュータサイエンスであった。また、自身の作品を発信する場であるウェブサイトについては、それ自体が1つの作品であると言うことができ、常に動的なものにしていきたいと考えている。
text=code=sound=performance
ピーリンガーは作品について語るにあたり、まず自身にとっての「text」の捉え方が述べられた。ピーリンガーが作品に用いる主な「text」はアルファベットであるが、「text」自体を、それぞれの文字が表す記号、プログラミングのソースコードというように、様々な意味を表す「code」として捉えると、「text」=「code」であると言うことができる。また、「text」を読むと音が発生するという点から、「text」=「sound」とも捉えられる。そして、「text」を音声として読み上げること、頭の中で読み上げること、PCにおいてソースコードとして実行することを、「performance」として捉えることができるのである。
ピーリンガーは作品制作において、素材としてのテキスト、音としてのテキスト、画像としてのテキストを使用することを重要視している。また、静的で変化しないものよりも、動的なシステムに関心があり、インタラクションや動的なテキストを実現したいと考えている。さらに、複数の人間の同時操作による、ソーシャルインタラクションにも関心を持っている。
computer poetry
「computer poetry」は決して新しいジャンルの詩ではないが、現代においてその制作にコンピュータを使用することは、大量の作品を制作できる点で重要である。歴史的には、石碑にグリッド状に刻まれた文字を、上下左右どちらからでも読むことができる、数学的な文字配置のなされたローマ時代の『latin poetry』や、ドイツのバロック時代に登場した、機械によって新しい言葉をつくり出す『baroque poetry』などが挙げられる。
そして1960年代、フランスの数学者、フランソワ・ル・リヨネーらによって「oulipo」という重要な文学グループが設立された。
彼らは固定された形式や、数学的な規則などといったプログラムの指示に基づき、詩を制作した。簡単な例としては『N+7』が挙げられる。 このプログラムは、文章中の名詞を辞書で調べ、その単語を7行下の文章にある最初の名詞に置き換えるというもので、既存の文章を置換する1つの方法である。できた文章は文法的には正しいが、意味のないものとなる。同じく、レーモン・クノーの『1014 poems』も有名な例である。これは、14行からなる詩であるソネット10篇を、1行ずつ切り離し、組み合わせておいたものを、任意に並べ替えることで、10の14乗、すなわち100兆通りの読み方が生まれるものである。他にも、グラフから既存の文章をどういう順番で読むかというルールを構築したものもある。「oulipo」の制作方法は、コンピュータによる作詞に通じるもので、実際に1970年代以降、「oulipo」でもコンピュータを使用した制作を開始した。
以上の歴史的背景をもとに、ピーリンガーは自作について語った。
『nam shub micro』はテキストのためのPhotoshopというコンセプトのもとに制作した。このシステムでは、入力したテキストを複製、綴りの組替え、分割など、コンピュータの演算によって様々な方法で編集し、音声で読み上げることによって詩を制作することができる。また、別のプログラムでは、1つのアルゴリズムから無限大の数の詩をつくりだそうと考えていた。例えば、『spellchecker poems』は、専用の言語データベースを用いて、ある単語と綴りの似た15の単語を抽出する。さらに、それらの単語に対して同様のアルゴリズムを実行することで、それぞれに新たな15の単語を抽出する。これにより225の単語からなる詩が生成され、PCがそれを読み上げる。様々な言語データベースを使用するため、例えば、ドイツ語では省略語が多く抽出されるなどといった、言語自体の特徴や各単語自体の特徴を得ることができる。
sound poetry
音は詩にとって重要な要素である。ピーリンガーはその中でも、テキストの音そのものに焦点を当てた詩である「sound poetry」について、自身にとって重要な2つの例からその歴史を語る。
まず、第一次世界大戦中のスイスで、フランス人やドイツ人を中心に、戦争と戦争プロパガンダに抵抗した芸術運動、ダダイスムにおいて、その作家の1人であったオーストリアのラウル・ハウスマンが、1つの方法としてランダムアートを用い、木版活字の無作為な組み合わせによって、言葉としては意味のない文字が並ぶ、「ポスター詩」「文字詩」と呼ばれる詩を制作した。本来これらは印刷物による作品であったが、ハウスマンの周辺のパフォーマーが読み上げることで、パフォーマンスへと変化していった。
そして、第二次世界大戦後、フランスのアンリ・ショパンが『The Body Is A Sound Factory』において、「sound poetry」に電子機器を利用し始めた。ショパンは、自身の身体は音の工場であると考え、言葉とは言うことのできない発声音を、テープレコーダーに録音し、その音声に重ねて新たな音声を録音するなどして音の素材を制作した。さらに、音響エンジニアではなかった彼は、敢えて正しくない使用法で音声を編集、加工し、新しい音をつくりだした。結果として作品はミニマルなものとなったが、他にはノイジーなものもある。いずれにしても、音の素材として利用されたのは、自分の声と、それをテープレコーダーによって加工した音声のみである。
以上の2作品がピーリンガーにインスピレーションを与える理由として、1つには音の素材に、声を使用している点が挙げられる。使用する声は、自身の声のみに限らず、他人の声を使用することもあるが、声というものが、身体の一部であり、身体から切り離すことができず、他人のものにはなりようのない、特別な音であることが重要なのである。また、技術を使用している点からもインスピレーションを得ており、ショパンが音の加工にテープレコーダーを使用したのに対し、ピーリンガーは新しい技術であるコンピュータを使用し、「sound poetry」を制作した。
また、インタラクティブな「sound poetry」である『soundpoems』シリーズは、flashによってインタラクションを実現したwebのための作品群である。『soundpoem three』は、異なる発音のテキストのドットをドラッグして、ボックスに入れると、そのテキストの音が鳴るもので、複数のドットとボックスの組み合わせを操作することで、曲を制作することができる作品である。続く『soundpoem four』も、アルファベットをドラッグしてボックスに入れ、音を発生させる作品であるが、ここでは1つ1つの文字それぞれが異なる挙動をとる。例えばIは好奇的な性格を持ち、他の文字を攻撃する性質を持つ。逆に、他の文字から逃げる性質を持つ文字もあり、1つ1つの文字が小さな脳を持ち、生物のように動き回る様子がみてとれる。
apps
2008年に『soundpoems』を制作した後、以前から関心のあったiOSアプリを制作した。初めて実験的に制作した『abcdefghijklmnopqrstuvxyz』は、『soundpoems』の機能をまとめたものであり、驚くべきことにいくつかの賞を獲得し、人気のアプリとして成功した。
『abcdefghijklmnopqrstuvxyz』はアート作品として成功したが、次作の『gravity clock』は、アートというよりはデザインとして制作した。これは、時間の経過を文字がこぼれ落ちる動作で表現したアプリであったが、金銭的にも収入を得ることができた。作家は普段から、自身の作品をどう売るかという問題を抱えているが、実際、パフォーマンスによる報酬はあっても作品を売ることは少ないため、アプリによって収入を得たことには意味があった。
最新のアプリは音楽アルバム『konsonant』である。音楽家であるピーリンガーは、以前CDを制作、販売したこともあるが、現状の音楽ビジネスには違和感を感じており、次作はアプリという形式で発表したいと考えていた。『konsonant』はインタラクティブなアプリであるため、使用者は曲をつくることができ、これは『abcdefghijklmnopqrstuvxyz』に続き賞を獲得した。
performance
パフォーマンス作品について述べる前に、ビジュアル作品『broe sael』が紹介された。これは、フィールドレコーディングによって音声を記録し、その音声を素材として音源を制作したのちに、テキストの映像を付加したものである。音の素材には、ドイツ語で語られた株式市場についてのレポートを、テキストには、株式市場についてのチャットルームでの会話を使用した。抽象的な作品ではあるが、ドイツ語が分かれば株式市場についての単語をききとることもできる。『broe sael』の完成時、ビデオの映像と音に自身の生の声を重ね、パフォーマンスを行ったが、ビデオ自体が固定的な要素であり、そのトラックに合わせてパフォーマンスしなければならないことに違和感を感じ、より柔軟な方法を考えるようになった。
その後、初めて試行した作品、『frikativ』では、音源は前作と同様、固定のものであったが、映像は完全にライブで、リアルタイムで音声に反応するものとなった。完全なライブとはならなかったが、当時のPCのスペックやプログラミングの技術を考えれば、満足のいく内容であった。前作に比べて視覚的にはプリミティブであったが、失敗や即興が起こり得る可能性があり、観客にとってはおもしろいパフォーマンスでと考えられる。
最新作の『abcdefghijklmnopqrstuvwxyz』は、完全にライブのパフォーマンスとなり、視聴覚融合の作品を目指すべく、音、声、映像の出力全てをリアルタイムで行った。プログラミングはより複雑なものとなり、ゲームエンジンほどの規模が必要であった。スクリプト言語を利用してゲームエンジンを制御し、1つ1つの文字に挙動を与えるために物理シミュレーションを行った。音を出力するエンジンを加え、コンピュータによって完全に制御できる動的なシステムを実現したことにより、ステージでの即興が可能となった。それぞれの要素はコードのアルゴリズムによって自立できたが、1つ1つの細かな制御は不完全であるため、映像と音に関しては満足しておらず、現在、改善に取り組んでいる。
The Vegetable Orchestra
ピーリンガーは最後に、以上の作品とは全く異なる、変わった方法で生成する作品、『The Vegetable Orchestra』を紹介した。この作品は詩でも電子音楽でもなく、10人の奏者が、野菜だけでつくられた楽器をライブで演奏するというものである。カボチャのドラムやニンジンのフルートなど、演奏に使用する楽器は、市場で材料となる野菜を購入し、ドリルや包丁を用いて演奏者自らが製作する。
ディスカッション
質問者:パフォーマンスにおいて、プログラミングによって生成される音と、自身の声を同時に発生することについて、どのように考えているのか?
ピーリンガー:ステージ上ではできるだけ何も考えず、自身の声によるライブパフォーマンスのみに集中することを目指している。自身の思想や考えは全て事前にPCに入力しておき、パフォーマンスの際はプログラミングコードを実行するのみである。
(河合由美子/IAMAS 学生)
ヨルグ・ピーリンガー Joerg Piringer
1974年生まれ。オーストリアの詩人、音楽家、プログラマー。 Institute for Transacoustic Research、ウィーン・ヴェジタブル・オーケストラのメンバー。音響詩、視覚詩、電子音楽、ラジオ・アート、コンピュータ・ゲームの分野で活動し、 近年はiPhoneアプリの開発者としても知られる。2010年アルス・エレクトロニカ・ホノラリー・メンション受賞。
(レクチャーで紹介された作品はこのWEBサイトで見ることができます)
ジャン=マルク・ペルティエ