安藤泰彦
前林明次
小林昌廣

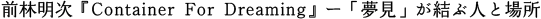





会場からの質問
-世界の中心大垣で未来の文化を考える-
シリーズ:a.Laboからの応答 #2P
前林明次(サウンド・アート)
『Container For Dreaming』- 夢見が結ぶ人と場所
a.Labo第2回目のプレゼンテーションは、主に音を素材としながら、身体と場所の関係性の問題を提起するアーティスト、前林明次が担当した。
はじめに、2011年に発表された『Container For Dreaming』が紹介される。この作品は、イベント「歌舞伎町アートサイト パブリックメディアアートの挑戦」に出品され、その舞台である新宿区歌舞伎町のシネシティ広場において展示された。
シネシティ広場に複数のコンテナが設置されており、その中のひとつが前林作品である。コンテナの中にはベッドが置かれている。体験者はその上で横になり、「夢見」を行う。コンテナ内部の前後両面の四隅には計8台のスピーカーが取り付けられており、新宿の複数の地点(歌舞伎町シネシティ広場、西武新宿駅前、新宿駅西口の地下通路、西口方面の高層ビル地帯の歩道橋、新宿中央公園、花園神社など )で録音された環境音が発せられる。8台のスピーカーから発せられるそれぞれの音は、 ベッドの上で寝ている体験者の頭の位置に集まる(頭の位置が、環境音を録音する際のマイクの位置となる)ように制御されている。連続した空間の環境音が8方向から聴こえることで、体験者は空間を立体的に把握することができる。
各地点の音は連続的につなげられている。そして、時間の経過の中でその音量は増減を繰り返している。緩やかに、かつ連続的に音量は大きくなったり小さくなったりを反復する。このような操作は、コンテナの中の環境音、つまりコンテナの中に聴こえてくる外(歌舞伎町)の音を前提としている。コンテナの外から聴こえてくる環境音(外の音)と、コンテナ内部のスピーカーから発せられる音(内の音)との関係を簡略化すると、次のように言うことができる。内の音の音量が大きくなったとき、外の音は聴こえない。内の音の音量が小さくなったとき、外の音は明瞭に聴こえる。音量が移行する過程で、外の音と内の音の境界が常に揺らいでおり、それによってコンテナの境界が揺らぐような効果が得られる。そしてそのような効果の結果として音量の操作が要請されている。
前林は「歌舞伎町アートサイト」に際して、『Container For Dreaming』の他にもう一作品、1999年に発表された『Sonic Interface』を出品している。体験者は用意されたショルダーバッグ(中にコンピューターが入っている)を持ち、ヘッドフォンを装着して街を歩く。ヘッドフォンにはマイクが付いていて、そこに入ってくる音はバッグの中のコンピューターでリアルタイムに加工され、ヘッドフォンへと出力される。コンピューターは拾われた音を遅延させ、断片化し、左右の方向を入れ替え、それらを出力する。歩いている街の光景に、加工されたそのような音が重なることによって、そこでの体験は特異なものとして立ち現れてくる。
『Container For Dreaming』と『Sonic Interface』を同時に出品したのは、いずれもその作品体験が、体験者にとっての場所の記憶となるからである。つまり作品装置によって人と場所とが結びついているというのがその理由であると前林は述べる。そしてここで、『Container For Dreaming』を考えるための三つのキーワードが挙げられる。
・stow away
・代償的内側性
・dreaming
1. stow away
「stow away」は、日本語にすると「密航」や「潜入」といった意味となるが、1979年にソニーが発表した携帯型カセットプレーヤー「ウォークマン」のイギリスでの商標が、当初は「Stowaway」とされていたことに前林は着目する。自分の好きな音楽を聴きながら街を歩くという行為が、「密航」や「潜入」といった意味へと結びつけられる。都市空間ではそのとき既に規律としての制度が充満しており、もはや個人的な空間とは相容れないものとなっていたということができるだろう。ウォークマンは、そのような都市空間への合法的な「密航」、「潜入」を可能にする装置として登場する。
前林は1967年に発表されたギー・ドゥボールの著書『スペクタクルの社会』を手掛かりに、都市空間の内に予め用意されている行為や読解の方法を無批判に受け入れるのではなく、それとは異なる方法で、そこからあえて逸脱していくという、西洋におけるひとつの社会的なムーヴメントを確認する。都市に対する抵抗。都市の中で何らかの行為を課す形式のメディアアート作品は、ほぼもれなくそのような文脈の中に位置づけられ、バルセロナやロッテルダムなど、様々なメディアアートの展覧会に出品された『Sonic Interface』についても、それは例外ではなかった。
そもそも『Sonic Interface』が問題化したのは、「歩行」時における「知覚」の有り様および、それらの関係性であり、作品の成立過程においてはドゥボール的な試みとしての意識があったわけではなかったと前林は述べる。「スペクタクル」を経由するそのような解釈は、同様の言説が西洋の各地で自らの作品を取り巻き続ける中で意識されるようになったものである。しかし、それと同一の文脈を日本にそのまま置き直せるかというとそうではなく、日本あるいは東京はそれとは別の流れ、歴史を持っている。そしてその場所の差異、流れの差異が、「密航」性、「潜入」性と新たな関係を結ぶ。新宿・歌舞伎町に設置された『Container For Dreaming』は、コンテナに入ることによって歌舞伎町のど真ん中へ「密航」することを可能としている。
展示期間中、その場所に滞在し続ける中で前林に感知されたのは、「どういう人がどういうタイミングで来ているのか」ということについての予測不能性、そのとりとめのなさだった。歌舞伎町は非常に猥雑な場である。曜日や時間で人々の交通が大きく変化し、それが規則的であるというわけでもない。様々な種類の人々がその場を行き交い、継続的にその場に居るのはホームレスやガードマンに限られる。
設営の段階からそれを眺めているホームレスが作品を体験するという可能性は十分に考えられ、作品における匂いの問題をどのように決定するかということも考えていたが、結局のところ彼らが作品を体験しにくることはなかった。しかし晴天のある日、ホームレスの人々がコンテナの周囲に集まってきて、そこで昼寝をし始めたことがあった。
ところで、歌舞伎町ではなく、銀座や渋谷といった街でコンテナの展示が可能かどうかということを考えると、やはりそれは一筋縄にはいかないだろう。一方では、割れ窓理論から発生した「ゼロ・トレランス」的な態度が見出す隙や例外性の「排除」が徹底され、他方では、街の持つある種のエネルギーによって「排除しきれないもの」が湧き出してくる。ここでは「排除」のひとつの例として、ホームレスがそこで寝たり、段ボールを置いたりすることを阻むという唯一の目的に特化した排除系アートと呼ばれるオブジェが紹介された。そして歌舞伎町はといえば、「排除」と「排除しきれなさ」の双方が拮抗している。「歌舞伎町アートサイト」のように、この場所の有効利用(クリーン化)の一環として始められたイベントにおいて、そこに設置されたコンテナの周囲ではホームレスの人々が昼寝を始めるのである。
コンテナは大別すると次の四つの意味において説明される。
a. 猥雑な環境への潜入
b. 無防備さを保護するシェルター
c. 内と外を分ける
d. 夢の「容器」
体験者は、都市へ潜入し、匿われながら、境界の揺らぎの中で、夢を見る。
2. 代償的内側性
地理学者エドワード・レルフの著書『場所の現象学』(1976)では、場所に対する人間の感覚として、場所に属している感覚(内側性)と、場所に疎外されている感覚(外側性)の二つが提出されている。その中で前林が注目する「代償的内側性」とは、訪れたことのない場所を、小説やテレビ番組などの体験によって、訪れた場所であるかのように感覚する性質であると簡約することができるだろう。
前林は前日に訪れたという金生山・明星輪寺(大垣市赤坂)での体験を語る。そこでは巨大な岩がまるごとお堂の中に収められている。この場所は疑いなく聖地である。いびつな形状の巨大な岩があり、それはそれ自体でエネルギーに満ちている。ひとつの場所の帯びるオリジナルなエネルギー、それをここでは「アウラ(オーラ)」と呼びたい。場所があり、力があり、それを人間が解釈し、認めてゆく。そこには歴史的な過程が存在するだろう。聖地とは元々、そのような場所とアウラとの関係性を基に成立してゆくものである。
対して美水かがみ原作のアニメ『らき☆すた』に登場する神社のモデルとなっている埼玉県久喜市の鷲宮神社は、アニメファンによって当該作品の聖地として扱われ、多くのファンが参拝に訪れている。これはつまり代償的な経験によって、場所に意味が付与されるというひとつの例である。前者は岩のオリジナルなエネルギーとその歴史性によって、後者はひとつの場所を異なる文脈においての聖地とすることを可能にする補足的な経験によって、それらの場所は聖地となっている。
ある場所からどのような情報を取り除き(脱埋め込み)、どのような情報を付与する(再埋め込み)か。近代以降、情報の「埋め込み」操作によって人と場所との関係が形成されており、今やそこからは逃れられないのではないだろうか。そのように考えるとき、再埋め込みによって人と場所との関係を作っていく際に問題となってくるのは、いかに「いい再埋め込み」ができるかということである。そしてその契機として、アート作品というものの可能性を考えることができるのではないだろうか。作品の体験が場所の経験となり、場所が作られていくということについて考え、それを積極的に捉えていきたいと前林は述べる。
メトロノームによって場所への再埋め込みを試みたと言える自らの過去作品『Metronome Piece』が紹介される。
3. dreaming
dreamingとは、ここでは場所について「想う」こととする。想う、すなわち目を閉じ、眼前にない事物について心を働かせるということである。『Container For Dreaming』の8台のスピーカーから流れてくる音、およびコンテナ内へと漏れ入ってくる外の歌舞伎町の音は、体験者のうちに空間性と場所を想起させる。dreaming=「夢見」の作用によって、自分と場所との関係性を構成し、統合することができないだろうか。そのような関係性を作り出すのは、情報としての「音」ではなく、行為としての「夢見」であり、メディアとしての身体である。
ローリー・アンダーソンの『Institutional Dream Series』(1972-1973)が先行作品として挙げられる。様々な場所で眠り、その場所性が夢に対してどのように影響したかということを記した文章を、その場所で寝ている写真と共に展示するというものである。しかしこの先行作品がそのまま『Container For Dreaming』と並列に語られてしまうべきではない。70年代のニューヨークは政治的な空間と個人の自由との間に明確な対立軸が走っていたが、2011年の新宿において、そのように際立った対立性を見出すのは困難である。前林が人類学者中沢新一に依拠しつつ指摘するのは、都市における対立性ではなく、混在性である。新宿は、歌舞伎町的なじめじめとしたエネルギー(排除しきれなさ)と、清潔で安全な乾いたエネルギー(排除)とがそれぞれ対立するのではなく、相互に入り組んでいる。新しいものの乱立が目を引く中で、特有な力を持つかつての痕跡を様々な場所に残しているのが東京という街である。
ローリー・アンダーソンと同時期、大筋では同様の文脈を背負いつつ、ゴードン・マッタ=クラークやトリーシャ・ブラウンなどの諸アーティストによって、街への介入が試みられていた。前林は現在、それらのリサーチを続けている。
続いて、作品体験の要素が五種類挙げられる。まず体験者が訪れる新宿という「場所」。次にそれぞれが持っているその「場所のイメージ、記憶」。そして、「その場にいながらにして、コンテナの中で横たわること」。現代において、主体と場所との関係は概ね、代償的内側性、すなわち付加された情報あるいはそれに基づく体験によって作られている。つまり場所とは、不自然さおよび倒錯性をそこに含まざるを得ない。『Container For Dreaming』が、シネシティ広場にいながらにして強引にもコンテナという特殊な空間に入るよう体験者に求めるのは、場所との関係を組み直すためであり、そのためにはその強引さおよび不自然さは必然であるのだ。
4つ目の要素は「音=テクノロジー、『新宿』のようなもの」。音は立体音響のテクノロジーが使用されており、出力されるのは歌舞伎町のみならず新宿の複数の地帯で録音されたものである。体験者は特定された場所の音としてではなく、およそ「新宿のような」音としてそれを聴くことになる。そうした音を夢のガイドとしながら、体験者は場所を想う(dreaming)のである。
そして最後の要素が「夢見、場所のシンセサイズ」とされ、ここではそれぞれに不連続な諸知覚と諸記憶の統合が問題となる。前林は、作家リチャード・パワーズによる、映画を見る際の反応についての記述を紹介する。「わたしたちはフィルム上の出来事に反応しているわけではなく、自分の心の中において同時進行で編集している千のリールに反応している」。わたしたちの反応はひとつの時間と空間に限定された出来事に対するものではない。それは数多の時間と空間についての同時的な反応である。ひとつの情報の断片は、あらゆる時間と空間に散らばった記憶の断片を現在へと浮上させるだろう。『Container For Dreaming』では、知らないけれど知っているような、新宿のような音を聴きながら、自らの新宿の記憶を引き出しながら重ねていくという行為が想定されている。「夢を見る」とは、無意識における断片的なサインを、意識的な方法とは全く異なる方法で統合しようとする身体の作用であり、その意味においてこの作品における「場所」は、ひとつの「夢を見ること」となっている。
「場所」と「夢を見ること」についてのそうした同義的関係は、アボリジニにおいてその近似値を確認することができる。アボリジニにおいてdreamingという言葉は、「神話の世界」と「夢を見ること」を同時に指している。アボリジニの描く絵は、神話時代のものと、現在の自分たちを媒介するものとしてある。絵だけにとどまらず、様々な儀礼がそれらの繋がりを創造するものとしてある。そこからわたしたちは、既にある状況に対して、創造的に合成、介入するという示唆を読み取ることができるのではないだろうか、そうして環境を作っていくことが必要ではないだろうかと前林は問いかける。
++++++
前林は「3.11への応答」と題された三月末の公開打ち合わせにおいて自作を紹介している。引き続きそのような文脈の中での自らの創作について考えていると述べられ、三つの観点が挙げられる。一点目は「テクノロジーと人間の関係性の問い直し」、二点目は「暗黙知、贈与性」、三点目が「『夢』の可能性」である。暗黙知とは、身体における知るという作動であり、知識に還元され得ない身体的な能力によるものであるということもできるだろう。それはつまり想像的な能力であり、換言するならば人間の「可能性」である。
「知るという作動」と同様に、夢にもまた、意識が計り知ることのできない何かが備わっている。夢にしても、身体の知るという作動にしても、それらを意識的に無意味なものとして抑圧してしまうのではなく、ある種の贈与として受け取り、十全に発揮できるようにするほうが良いと考える。それをいかに手助けできるか。テクノロジーを使いながら、夢や暗黙知をいかに発現させるようなものにできるか。そうした問いを携えながら制作していきたいということが最後に述べられ、前林のプレゼンテーションは終了する。
(佐原浩一郎/IAMAS 研究生)







