マルチバース化し、量子化する世界へ
岐阜イノベーション工房2020シンポジウム : 都市の“辺境”(フロンティア)レポート
2020年5月27日、岐阜イノベーション工房が主催するシンポジウム「都市の“辺境(フロンティア)”」がオンラインで行われました。本企画は、情報科学芸術大学大学院[IAMAS]が2018年度より展開する取り組み、岐阜イノベーション工房の公開イベントとして、2018年度「テクノロジーの“辺境(フロンティア)”」、2019年度「IoTの“辺境(フロンティア)”」に続いて開催されました。
ゲストに建築家・豊田啓介さんを招いた今回は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて初めてのオンライン開催となりましたが、この日はつい2日前の5月25日に緊急事態宣言が解除されたばかりという頃。この状況下で、物理空間と情報空間における人と人との距離が大きく様変わりしようというなかで問い直される「都市」の辺境を考えようとする本企画は、画面越しの話者に感じる新鮮な臨場感もあいまって、様々な示唆に富む議論の場となりました。その様子をレポートします。
新型コロナ禍における大転換
はじめに、本企画のホストである同大・小林茂教授の基調講演では、この新型コロナウイルス感染拡大に伴う世界的な生活様式と価値観の大転換における気づきと実感が語られました。大垣市で隔年開催されるDIYの祭典「Ogaki Mini Maker Faire」の総合ディレクターも務める小林さんは、本年5月に開催予定だった「Maker Faire Kyoto 2020」の中止と、それに代わるオンラインでの開催に、新しい展開を見出します。メイカーフェアの醍醐味は、つくり手である参加者が各々に作品を持ち寄り、それをどうして、どのように作ったかをオンサイトでシェアすることにあります。これがオンラインで成立するのかが危惧されていたわけですが、実際には、オンサイトの代わりにTwitterに投稿された参加者による作品は千件近くにのぼり、むしろ従来の空間的な制限の中では見せづらかった、作品制作のプロセスや背景などの詳細な公開・共有が可能になっていたのです。
同種の気づきは、例えば山口情報芸術センター[YCAM]で毎年開催されてきたワークショップ型の「運動会」であるはずの「未来の山口の運動会」のオンライン開催に見られた参加者のクリエイティブな取り組みや、小林さんがIAMASで担当されている、これまでハンズオン形式で行われていた授業のオンデマンド型の動画提供への切り替えが意外に有用だった、ということにも表れています。物理空間における人と人との距離が離れる一方、情報空間における距離は縮まるなかで、それぞれに新たな手段が試みられているのです。
新型コロナウイルスが、感染被害や非常事態宣言/外出自粛による多大な経済的ダメージをもたらしたことは紛れもない事実ですが、そうした負の側面の裏側で、これまで漸進的な変化しか起きないと思われていた社会に、十年、あるいは数十年分の変革が一瞬にして訪れ、人々のものの見方・とらえ方を根底から変え、世の中を一変させる大転換が起ころうとしています。小林さんはこれを、「社会のほうが動いているときであれば、ちょっとした力であっても何かを起こせる」、ある意味ではチャンスなんだと言い、今こそイノベーションの本質を理解し、広い視野で世界を眺めていく必要があると説きます。
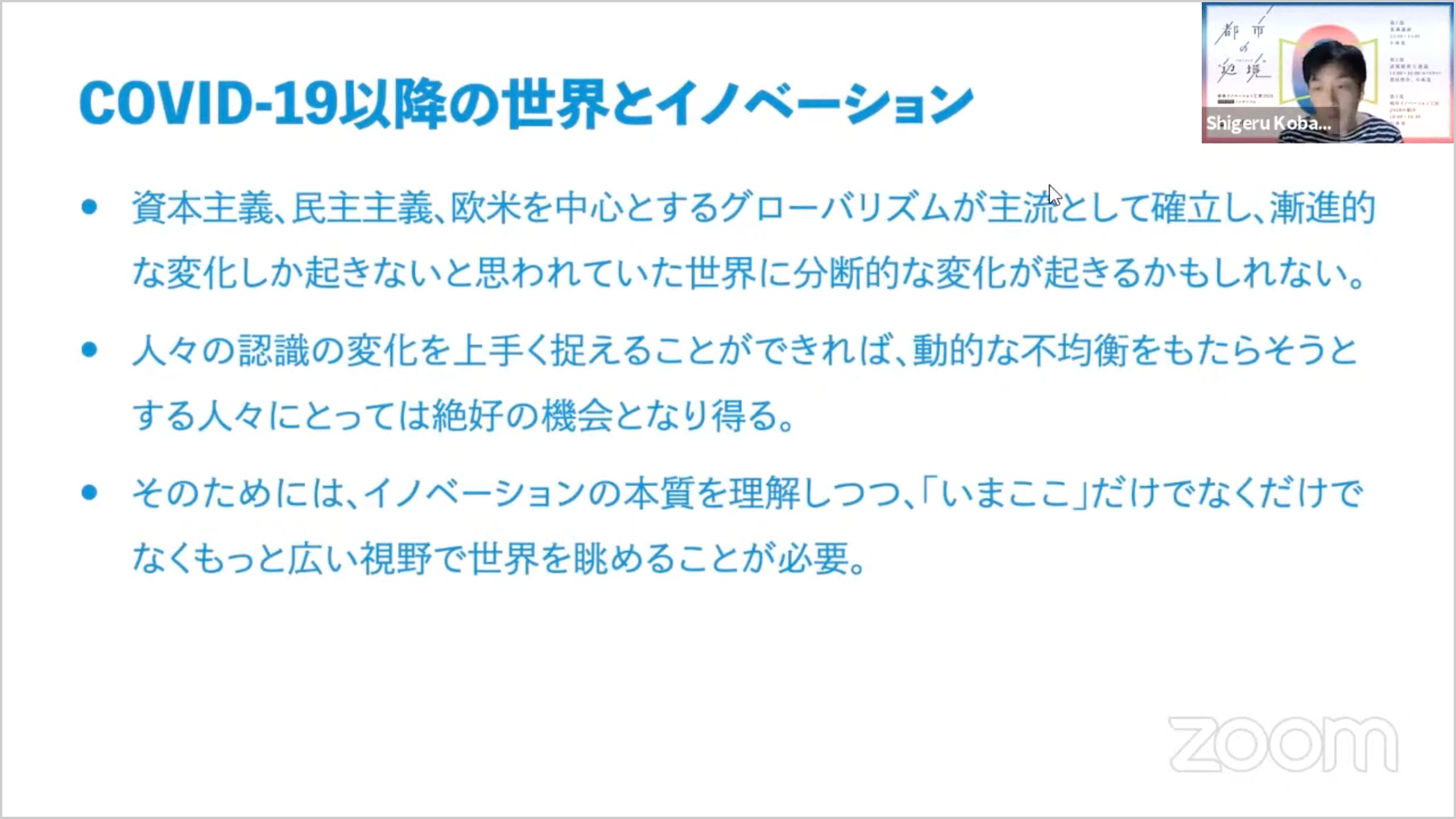
「イノベーション」とは何か
イノベーションを正しく理解するにあたって、小林さんはまず、国内における「イノベーション=技術革新」の誤解を指摘します。この語は、「もはや戦後ではない」の言葉で知られる、1956年『経済白書』(経済企画庁)の中で「技術革新」と訳されたことにより、新技術の発見や開発に限定されるようなイメージを持って広まってきました。この語は、オーストリアの経済学者ヨーゼフ・シュンペーターにより、1912年『経済発展の理論』によって初めて定義されましたが、停滞する当時のオーストリア経済を大きく動かすためには、企業家がそのバランスをダイナミックに崩すべきだと主張し、この考え方を「新結合の遂行」とし、イノベーションの概念を提唱しました。シュンペーターはイノベーションを5つに分類し、1.新しい商品・品質の開発、2.新しいの生産方法の開発/商品の新しい取り扱い方、3.新しい市場の開拓、4.新しい資源の獲得、5.新しい組織の実現、と定義づけており、技術革新をも含むものの、本来は幅広い概念であったことがわかります。
その後、しばらくは注目されないでいたイノベーションの概念は、経営学者ピーター・ドラッカーが再び着目しました。例えば、1985年の『イノベーションと企業家精神』で詳しく言及しています。以降も2005年に経済協力開発機構(OECD)、2013年に欧州標準化委員会(CEN)などによって引き継がれ、洗練されてきました。このように、社会の発展におけるイノベーションの重要さは国際的な了解のもとにあるわけですが、国を問わず、既存組織にイノベーションを生み出していくことは容易くはありません。その課題認識から、2019年には、イノベーションの実行を助けるものとして、イノベーション・マネジメントシステムの国際規格が発行され、イノベーションの重要性は益々高まるものと思われます。
ここで、そんなイノベーション創出の方法の一助として、任天堂にて『ゲーム&ウォッチ』や『ゲームボーイ』の開発に携わった横井軍平の哲学である「枯れた技術の水平思考」が紹介されました。「水平思考」とは元々、1967年にエドワード・デボノが提唱した概念で、論理的・分析的な「垂直思考」の対概念とされます。垂直思考が過去の延長線上に未来があるような、積み上げ型の、直進的な思考として日常生活に必要とされるのに対し、確実性が低く脇道にそれるものである水平思考は新しいアイデアを生み出すのに有効だとされました。これを援用し、横井は「技術が枯れる」=技術が普及しコストが下がるまで待ったところで、これを水平思考して新しい利用方法、つまり新結合を探る、ということを述べているのです。これまでの価値観さえ一変させる、新型コロナのような大転換にあっては、従来の社会システムや生活の延長線上ではなく、こうした水平思考にこそ活路が見出されるのかもしれません。
現代のフロンティアはどこにある?
建築家の豊田啓介さんは、そんな社会の大転換と行く末を見据えるように、コンピューテーショナル・デザインを積極的に取り入れ、かねてより物理空間のみならず、情報空間を同時に建築の対象としてきました。豊田さんは、今回のシンポジウムテーマである「都市の“辺境(フロンティア)”」に踏み込む前段として、「今のフロンティアはどこにあるのか」と問いかけます。新大陸の発見に始まり、西部開拓時代、あるいは月面着陸の競争に至るまで、人類は時代時代で陣取り合戦を繰り広げてきたわけですが、豊田さんは建築家として様々な実務に取り組むなかで、「フロンティアを物理世界の拡張に求めるという概念自体がそもそも成立しないんじゃないか」と感じるようになったと言います。そして、現代における新フロンティアは高次元領域だ、と説きます。
これはそもそも、建築家としての仕事における物質と情報の関係に感じた違和感が根差しているようです。ともすれば、物質と情報は二項対立的に考えられがちなものです。建築家という仕事は、空間や構造物といった3次元空間をデザインする者という認識が広く一般的ですが、実務のうえでは、工程や法律、構造、材料、環境、人やテクノロジーなどありとあらゆることを総合的に扱っており、価値体系としては50次元、100次元を扱うのだと言います。こうした高次元の情報は、しかし他者と客観的に共有できるわかりやすいメディアに落とし込んだ時に、2次元の図面や、3次元の模型/構造物へと、低次元化されてしまう。そこで望まれるのは、本来扱っている高次元情報を、高次元のまま書き出して、社会と共有する技術です。こうして知の高純度な外部化が成し得たうえで、物質から情報までがシームレスに繋がり、行き来できるようになることが目指されます。
都市のコモングラウンド
では、都市のフロンティアはどこにあるのでしょうか。豊田さんはこれに、京都大学大学院の西田豊明教授の言葉「共有基盤(コモングラウンド)」を引き、この必要性を説きます。これまでの建築や都市計画は、使い手である人間にとっていかに使いやすいかを念頭にデザインされてきました。しかしこれからの都市には、AIや自律走行の機械、画像認識・音声認識のシステムに、ARのアバターといった、デジタルエージェントの存在が不可欠であり、今の私たち物理エージェントに最適化された物理世界では不十分なのです。そこで、こうしたデジタルエージェントと、私たちのような物理エージェントの双方が認識され、デジタルエージェントと物理エージェントがシームレスにインタラクトできるようなコモングラウンドが必要になる、というわけです。具体的には、物質世界と、デジタルエージェントが認識しやすい形式で記述されたデジタルツインの世界が重なり合い、双方がそれぞれの環境や住人を疑似的に認識し合えるような基盤を差しますが、豊田さんのお話によると、これが意外なほど進んでいないのが現状です。
これには当然、AmazonやFacebookに代表されるようなプラットフォーマーが有利であるかと思えば、豊田さんはむしろ日本にとっていいタイミングだと言います。折しも、グーグルの親会社であるアルファベット傘下のサイドウォーク・ラボ社が進めてきた、カナダ・トロントでの未来都市「IDEA」構想は、今年5月にその計画中止が発表されました。これは米中型のITジャイアントによる寡占的、画一的な進め方の限界とも言え、一方で、巨大企業はなくとも、多数の企業を束ねることで資金力や十分な技術開発力を用意できる日本は、自ずと寡占を退けオープンな日本型を成し得るわけです。トヨタが東富士に計画するWoven Cityという先行例や、豊田さんも携わる2025年に控えた大阪万博で実証実験的に様々に試みることができるのもアドバンテージです。
また、豊田さんはこうしたコモングラウンドのあり方として、記述の仕様がモノの数だけ無数にあることに寄り添って、様々な仕様を束ねるプラットフォーマーが、階層性をもって、入れ子状に組みあがっていくかもしれないと言います。このとき、情報プラットフォーマーが完全優位に見える一方でモノを扱うノウハウを持っていない現況に対し、むしろモノづくりを得意としてきた日本企業にこそ、勝機が見えてくるとも言います。ここで、情報への苦手意識から抜け出し、モノから情報までをシームレスに扱える知見を獲得することで、日本企業はクリティカルに打って出ることができる、というのです。

マルチバース化し、量子化する世界へ
こうしたこれからの世界のあり方を、豊田さんはマルチバース(=多元宇宙)化、量子化する世界と言い表します。新型コロナ禍における外出自粛で、内(/家)と外との間にはっきりとした境界線が引かれたように思えましたが、生活の上では、自宅にいながら仕事をし、子どもの教育をし、同時に家庭生活をおくるというふうに内外の複雑化が起こり、また小林さんによって冒頭で紹介されたオンサイト/オンラインの関係においても、二者択一ではなく、リアルとバーチャルの往来/連環にこそ新しいあり方が目指されていたのでした。そのような時に、従来の二項対立的なモノ/情報、リアル/バーチャル、オンサイト/オンラインに足元をとられるのではなく、豊田さんをはじめとする建築家のように、異なる次元を軽やかなステップの水平思考で行き来することによって、次代を切り拓くイノベーションを獲得できるのかもしれません。

