「IAMAS 2019 場違いの場所で」を観て

「IAMAS 2019」第17期生による修了研究発表会および2018年度のプロジェクト研究発表会のテーマは、「場違いの場所で」という。「場違い」とはどういうことだろうか。また、「場違いの場所」とは。
メディア・アートと呼ばれる芸術表現も、これまでずいぶん「場違い」な思いをさせられてきた。たとえば、文化芸術基本法(平成29年6月23日に文化芸術振興基本法の一部を改定したもの)においても、「コンピュータその他の電子機器等を利用した芸術」は、メディア芸術と規定されており、文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊などのジャンルを含む、芸術から区別されているのはご存知の通り。もちろん現在では、「コンピュータその他の電子機器等を利用した芸術」のすべてを芸術から区別することは困難であるし、その規定自体があまり意味をなしていないように思われる。あくまでも便宜上の分類であり、「コンピュータその他の電子機器等」を含む、多くのテクノロジーを使用した芸術表現が、メディア芸術と規定される以前から、芸術の中で展開されてきたことも周知の事実である。ただし、それもまた長い間、ある種の「場違い」なものとして受け取られてきたことも否めない。
テクノロジーによる芸術は、これまでなかなか芸術と看做されてこなかった。1960年代後半、1970年の大阪万博へと向かう、日本におけるテクノロジー・アートの隆盛の時代から、メディア・アートが確立されつつあった1990年代半ば以降、現在にいたるまで、メディア・アートへの批判というものは、それがテクノロジーのデモンストレーションでしかないことにあった。いまだにメディア・アートが芸術であることをたしかめるために、それが芸術的な内容を持っているのか、あるいはテクノロジーでしかないのか、ということが問われる。なぜなら、テクノロジーそれ自体は芸術ではない、という半世紀以上にわたるアートとテクノロジーの齟齬がそこにはある。芸術とは人間の手仕事によって実現される崇高なものであり、対して、機械は無個性で画一的であるとされていた60年代当時には、テクノロジー・アートの動向は、あくまでも一過性の現象であると看做されていた。90年代後半、世界的にもメディア・アート・センターが設立されたり、美術系大学などに専門の学科が設立されたりするようになっても、当時はそれもまたどこか「場違い」なものだった。
「科学的知性と芸術的感性の融合を掲げる」IAMASは、1996年に岐阜県立国際情報科学芸術アカデミーとして創設されている。「科学技術と芸術文化の対話を促進」するという活動理念を持つICCもまた1997年に開館しており、同時期に活動を開始している。科学と芸術が融合とは、これまでなかなか相容れなかったふたつの文化が対話を行なう、学際的な場であるということだ。「異なる領域に積極的に足を踏み入れる」ことは、「場違い」な場所から/への介入であり、そうすることで、それぞれから見えなかった側面を発見し、再考するのである。IAMASの学生は、それぞれが異なる経歴を持った、ひとりひとりが別々の領域を専門とする人たちだろう。実際、展示も統一感があるようだがそれぞれ違う、また全体的な方向性が示されながら、個人やプロジェクトが、それぞれ独自に異なるテクノロジーへのアプローチを指向しているのがいい。当然、それぞれのメディア・テクノロジー観、メディア・アート観も異なることだろう。それは、学生たちがIAMASを「場違いな場所」としてとらえているということでもあるのだろう。学校内の展示や、学生の間だけで自足してしまうのではなく、自身が「場違いの場所」に身を置いていると考えることが、社会的な存在として自身をとらえることにつながる。
これまでも、IAMASにいたけれど「メディア・アートのことがよくわからない」、自分がいかにIAMASにおいて「場違い」か、ということを私に話してくれたIAMAS卒アーティストも少なくなかった。たしかに、どこかとても専門的に見えるし、それを共有できるある種の居心地のよさを感じさせるIAMASだが、それだけではない懐の深さを感じさせるのもまたIAMASなのだと思う。
前置きが長くなってしまったが、発表会について。まず小さなコーナーではあったが「池田町有線放送電話プロジェクト展示」に注目したい。「有線放送電話」というものの存在を初めて知ったということもあるが、しかも、それが半世紀に渡って行なわれてきたということ、またそれを記録し、残してきたということにはただ驚かされた。「池田町有線放送電話農業協同組合からの全面的な協力を得て、半世紀にわたる膨大な放送データが研究素材として提供された」、放送データの整理と保存を行なうということだが、こうした地域におけるローカル・メディアが、特定の状況下で半世紀の間使用され続けていたことの意味を考えることで、そのメディアの持つ可能性を研究するものでもあるだろう。1991年にICCプロジェクトの最初の実験であった「電話網の中の見えないミュージアム」も電話回線を異なるメディアに転用したものだが、そうしたもうひとつのメディア史を考えることもできるだろう。

池田町有線放送電話プロジェクト展示
テクノロジーがより一般化し浸透した社会では、その利用、応用の仕方も、研究のアプローチも変化している。芸術的表現は芸術から娯楽まで、また芸術的な発想と結びついたテクノロジーは、生きるための社会実践へと接近していく。メディア研究も過去の事実がいかに現在と切り結ぶことが可能かを考えていくことになる。
言葉を介さずに他者とひとつのものを共同で制作する「造形行為を通じて他者と繋がる」ワークショップを行なう、野呂祐人の《モノトーク》。特別支援学校の児童に、車椅子に脱着可能な「オープン・ハンドサイクル」を開発し、段階的に外出支援のためのワークショップ行なう、湯澤大樹の《特別支援学校の児童を対象とした外出への機運を醸成する試み》。また、「メディア表現学の分析手法を実践的に研究し、研究情報の文化資源化を実験的に実施」し、「つくる人、すむ人、みる人でつくるコミュニティ・アーカイブ」〈坂倉準三篇〉を制作した、メディア表現学研究プロジェクトや、福祉の技術プロジェクト、根尾コ・クリエイションなどの実践は、第三者がその方法論を継承した、継続的な実践となることでより波及していくことが目指されているだろう。根尾コ・クリエイションの「生きるための創造と技術」というタイトルは、テクノロジーとは人間が創造し、獲得し、継承してきた知恵の謂いなのだということを思った。

野呂祐人《モノトーク》

湯澤大樹《特別支援学校の児童を対象とした外出への機運を醸成する試み》

メディア表現学研究プロジェクト《つくる人、すむ人、みる人でつくるコミュニティ・アーカイブ〈坂倉準三篇〉》

根尾コ・クリエイション《生きるための創造と技術》
メディア・アート作品においても、技術を使用した表現の問い直しや、現在のメディア状況を反映した、テクノロジーをいかに批評的に扱うかという姿勢が感じられる作品が多かった。小濱史雄《displayed_scape》は、屋外でGoogle マップなどのインターネット上にある記号を建物などにプロジェクションし、ネット空間のアイコンを現実に重ね合わせる。ネット空間と現実空間が地続きになった、と言われるポスト・インターネット時代の風景の変容を考えさせる。ICCでも展示を行なった平瀬未来の《Translucent Objects》は、平瀬が「メディア空間における彫刻」と呼ぶ、メディアを介した視覚体験について考察するシリーズを展開したもの。ICCでの展示よりも要素が増えていて、VRなども使用した作品など今後の展開を期待させる。中路景暁の《Sequences/Consequences》は、どこか教育番組を思わせる、ベルトコンベアーをモチーフにした50のスケッチである。ベルトコンベアーの流れ作業は、チャップリンの『モダンタイムス』(1936)以来、機械化された工場の機械に制御された工業社会に翻弄される人間を描く格好の舞台となっているが、そこから50のさまざまな、しかもすべて異なるアイデアを考え出した労作。シンプルだが飽きさせない構成は、ジョン・ウッド&ポール・ハリソンを思わせる。尾焼津早織の《宇宙人、ひとり。/メリー・ゴー・ラウンド》は、マンガという表現のフレームワークを元にした映像作品で、モーションコミック(マンガを元にした映像作品)という手法なのだそうだ。アニメーションではなく、マンガのコマの読む順序とスピードをズームやパンニングによって設定したものだが、ページというフレームにとらわれないコマの構成が秀逸で、ストーリーテリングの可能性も感じさせるものとなっていた。

小濱史雄《displayed_scape》

平瀬未来《Translucent Objects》

中路景暁《Sequences/Consequences》
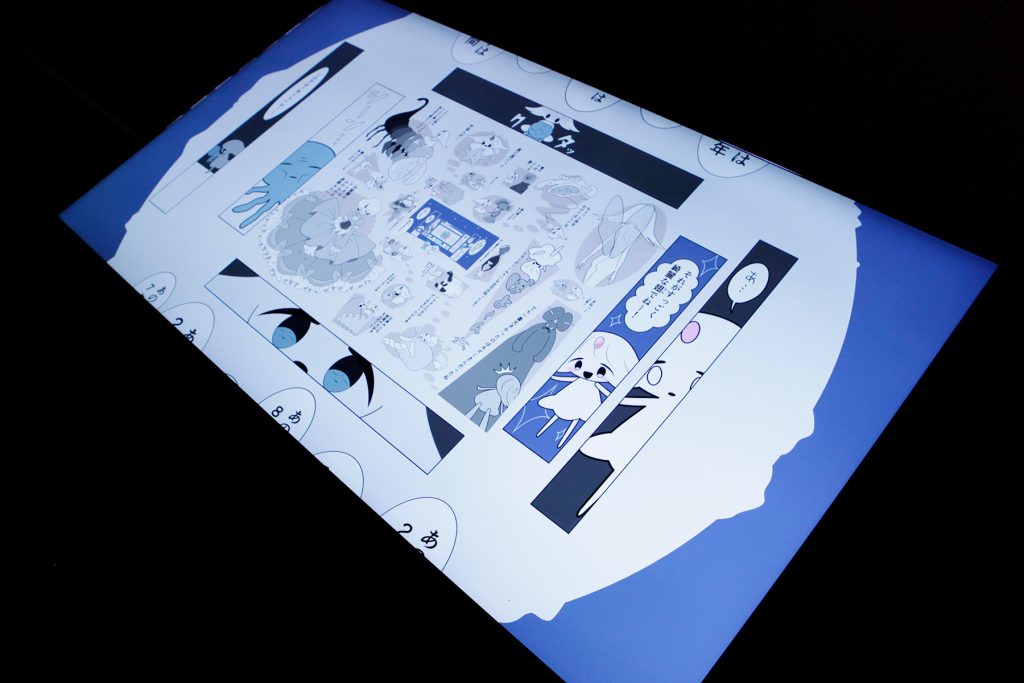
尾焼津早織《宇宙人、ひとり。/メリー・ゴー・ラウンド》
個々に言及できていない作品やプロジェクトがまだ多々あるが、テクノロジーやメディアによる表現や社会実装が非常に細分化された現在、メディアの可能性を探る試みもまた多様化している。いまいちどテーマに立ち返るならば、「場違い」であることを続けるためには、その場に馴染んではいけない。つねに部外者の視点を持ち続けることが必要だろう。
IAMAS教授安藤泰彦の退官記念展示として同時に開催されていたKOSUGI+ANDO《Sleepless Babies 2019 —眠れぬ子らのために》の展示は、そもそも自然界に存在していなかった、そして簡単に消え去ることのない、地球上でもっとも「場違い」な人工物についての作品であり、そうしたものと共存しながら、同じ技術をもって「生きるための創造」そして想像を続ける、地球にとってはそれもまた「場違い」なテクノロジーとの関わりを「場違いな場所」で続けることが、すなわち人間の営みなのだということを考えた。

