教員インタビュー:大久保美紀准教授

自己を超えて共感される表現こそが創作の本質
- 大久保さんは、美学の分野の中でも、メディア美学、特にデジタル環境やインターネット環境などニューメディアにおける自己表象をテーマにご研究されてきたかと思います。そういった研究を始められた経緯について教えてください。
京都大学にいたときはフランス人アーティストのソフィ・カル(Sophie Calle, 1953-)の研究をしていたんです。肉親の死や失恋、あるいは思い出という極めて個人的な主題を作品化する女性作家です。彼女の作品のように、コンセプトを作ったりルールの規則を作ったりするアーティストが気になって調べている中で、ニューメディアにおいて、どのように自己を表現するか関心を持つようになりました。
テクノロジーが誰しもの手に入るようになって、自分の表現したいもの、つまり「私」というものを皆が表現しやすくなって、一般の人がアーティスティックな表現に取り組むことができるようになっています。一方で、アーティストの方では、自分で手の込んだものを作るのをやめて、コンセプトを作ったり、あえてアマチュア的な方法で表現に取り組んだりする状況があり、お互いの表現がクロスして変わっていくところに関心を持っていました。
作家でない人々も表現をしている現代において、それをどのようにアートとして作品化していくのか、その表現を意味あるものとして作れるのか、どこに境界があるのか気になったんですね。
失恋や肉親の死のような、個人の思い出とか苦しみの話が、ある閾値に到達すると、個人の領域を超えてもっと一般的に共感され、共有されるレベルに至る次元にこそ芸術表現の力を感じていましたし、そういう表現こそをやるべきであると感じてきました。すごく個人的で親密なテーマから表現を出発する作家はとても多いですし、そういったことは人類の創作のモチベーションの本質です。
他にも、アイ・ウェイウェイやロマン・オパルカ、ピュ〜ぴる、松井智惠、石内都、ファッションデザイナーの創作や、サブカルチャー的な文化現象などさまざまな文脈の表現に興味を持って研究してきましたが、非常に凝ったものを作る場合でも自分の経験をベースにしながら、個人の範疇を超越して他者に共有されていく芸術表現には惹きつけられるものがあります。
- 京都大学の修了後にはパリ第8大学に移られますが、そこではどのようにご研究を展開されましたか。
パリ第8大学にいた時は、ブログについて考える中で、日本の平安時代の日記文学を調べていました。日記文学では、たとえば宮中の女性が自分の想いを綴っている場合でも、その日記が外に流通するとは想定していなかったにもかかわらず、今の私たちが読んでも文学作品として成立するクオリティで書かれています。
現代のブログも同じように、自分のために積み重ねて書いているんだけれども、それは読まれることを一応前提としている。文学作品ほど気張らずにもっと軽やかで自由なものとして、多様なライティングの可能性が追求されていると思います。単なるノンフィクションでもなくて、フィクションとして、自己演出するような形で日々の感情を表現して書いているブロガーもいますし、SNSでもある程度、自己演出的に書くことができるような環境があります。
それによって、個人的な問題を乗り越えることができたり、それを通じて読んだ人にも共感を与えたり、想いが伝わったりと、その人が変わる契機となる場合もある。そういうことが、今のメディア環境にはあると思うんですね。
では、それをどういうふうに作品化できるのか?
この問いを学生と一緒に考えて、私の担当する授業ではブログを使って創作をしてもらったり、Twitterを介してワークショップをやったり、個人的な物語を題材として自己表象をめぐる実験をしていました。たとえば、日記や手帳、思い出の品物とか、プリクラ帳を持ってきた人とかもいたんですけど。普通の人の「普通の思い出」を作品にする、ということが成立するのかどうか、そういう試みをしていましたね。
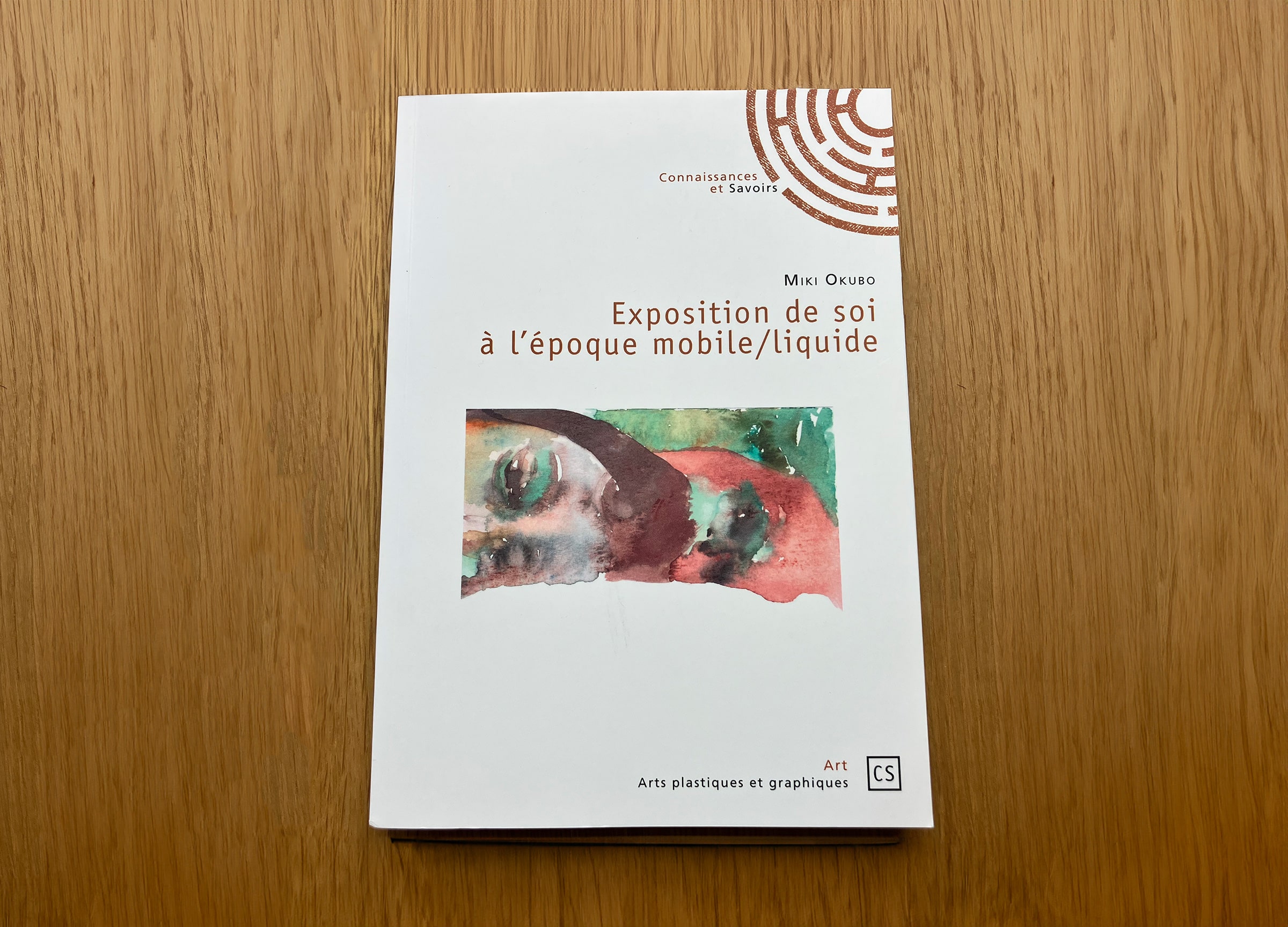
Miki OKUBO « Exposition de soi à l’époque mobile/liquide » (「流動的で可動的な時代の自己表象」)、2015年にパリ第8大学に提出した博士論文を2017年にConnaissances et Savoirs社から出版した。フランス語で334ページの長編に自己表現をめぐる芸術表現・文学・文化現象をまとめている。表紙の挿絵は古市牧子による。
そういうことをしているうちに、フランスのナント市にあるナント・サン=ナゼール高等美術学校を基盤に活動する数名の作家と親しく関わるようになったんです。彼らは大きくいうと「身体」の問題を共通のキーワードにしていて、それに関わるものとしての環境、食べ物、医療について扱う表現をしていました。
2013年から2016年頃まで、一緒に作品制作をしたり、展示やシンポジウムをしたり活動を共にしていて、エコロジーのような問題が自分の身体に直接結びついたものだという気づきをもらったんですね。この間、パーソナライズド・メディシンについてテキストとドローイングで考察した 《Vivre ou vivre mieux?》(生きる、よりよく生きる?, Jérémy Segard & Miki Okubo, 2015)をフランスのいくつかの都市で発表してディスカッションをしたり、感染症の寄生者と宿主についての展覧会 《L’UN L’AUTRE》(一方ともう一方, 2016-2017)に取り組み、4人の出展作家全員にインタビューして評論を執筆したり、展覧会全体の枠組みについてエッセイを書いたりして、今考えると、現在の研究テーマに踏み込んでいくための大事な時間だったと思っています。
その展覧会の企画者であるジェレミー・セガール(Jérémy Segard)と、パートナーで出展者でもあったフロリアン・ガデン(Florian Gadenne)を始めとするアーティストたちと一緒に、衛生の概念や近代医療の問題など、身体を基軸として医療やエコロジーのテーマを考えるようになって、「ファルマコン」という概念に出会ったのが自分にとって大きな転機になりました。彼らとは「ファルマコン」をめぐって、継続してプロジェクトや展示をすることになります。
「ファルマコン」からエコロジー概念の探求へ
- その「ファルマコン」とはどのような概念でしょうか?
「ファルマコン(Pharmakon, φάρμακον)」はギリシャ語で、薬学を意味する「pharmacology」や薬局「pharmacy」の語源となっている言葉ですが、「薬」と「毒」の両方を同時に意味するのに加えて、第3の意味として「スケープゴート(生贄)」があります。毒にも薬にも、どちらにもなり得るという意味ではなくて、あるモノはそれ自体がそもそも両儀的であるというふうに考えるべきです。これは、プラトンの『パイドロス』に基づいて書かれた短いテキスト《La pharmacie de Platon》の中で、フランスの哲学者のジャック・デリダ(Jacques Derrida)が再発見してよく議論されるようになった概念です。プラトンがそもそも指摘した「ファルマコン的なもの」、そしてデリダを参照したスティグレールの論を参考にしながら、今日、そういった両儀的なものを見直す必要があるんじゃないかって言うことを考え始めたんです。
現代の社会では、いろいろな問題で両極端になりすぎていて、二項対立的な考え方のもと「こっちかあっちか、はっきりしろ」みたいな暗黙の要請によって人々の決裂が起こったり、不一致によって折り合えなかったりしますよね。そういったことが結局、日常の人間関係のレベルから、コミュニティ、社会、国家や国際社会に至るまでいろんな問題に繋がっているはずで。たとえば、いき過ぎた衛生観念とか、コロナ禍における「ウイルスを撲滅せよ※」という考え方とか、生物レベルで良いとか悪いとかの判断を下すなど。(※フランスのロックダウンにおける国家的協力を訴える2020年3月16日の大統領演説において繰り返された「我々は今戦争状態にある!(Nous sommes en guerre.)」という表現に顕著に現れる。21分のスピーチにおいて6回も繰り返されたこの言葉は、ウイルスを仮想敵とすることによって国民を団結させる戦略的レトリックであった。)
もっと別の次元で話し合って、「中庸」というか、両方が本質的に共存するという状態を、見直していくべきじゃないかと思うんです。数々の問題に直面していく中で、ますます、このテーマについて、時間をかけて展開する意義があると感じるようになりました。
2018年から4年間、研究プロジェクト「現代社会における〈毒〉の重要性」(京都大学こころの未来研究センター主宰)に連携研究者として参加しました。吉岡洋さん、小澤京子さん、加藤有希子さんがメンバーで年度末に『ポワゾン・ルージュ』(poison rouge)という研究誌をまとめており、そこで「ファルマコン」の概念についてより深く、領域横断的に考え、いくつかの論考を執筆するきっかけになりました。展覧会のことはもとより、コロナ禍における離別と出産、菜食主義と現代の生、同毒治療(ホメオパシー)に関してなど、多岐にわたります。
- 「ファルマコン」をめぐる思索を深めていった結果、 エコロジーの問題を現在ではご研究の主軸に置いておられるんですね。
はい、これまでも「共感」を自分のテーマとしてきましたが、人間と人間のあいだで他者に共感するという、一般的に使われる意味での共感の話だけではなくて、人間じゃない存在までふくめた共感については、どんなふうに考えられるのかなと思って、エコロジーのテーマに繋がっていきました。
ただし、エコロジーというと環境の話をしていると捉えられがちなんですけど、いわゆるSDGsとか環境問題という狭義のエコロジーの話をしてるのではなくて。
私たちが一番大きい影響を受けているのはやはり、フェリックス・ガタリ(Félix Guattari, 1930-1992)の『三つのエコロジー』(《Les trois écologies》, 1989)なんです。それは社会と個人の精神の問題で、日常生活レベルのエコロジーであったり、家族やコミュニテイにおける問題、階級闘争のことや社会闘争のこと、フェミニズムの問題が複雑に絡み合っている地球規模の問題として、取り組んできたところです。
コロナ禍に開催した三つの展覧会(「ファルマコン:連鎖反応」2020, 「ファルマコン:死生への捧げもの」2021, 「ファルマコン:新生への捧げもの」2022)では、社会における死生感、死者や未来の人への配慮の欠如について考えたのですが、「共感」は想像力をいかに拡張できるのかという問題に関わります。人間中心主義を人新世的な文脈によってどのように乗り越えるかという問題系に対して、この「共感」という概念を拡張することで、人間と人間の間のシンパシーではなくて、非人間存在、モノ、環境、さらに外部へと共感の射程を広げられれば、この惑星の問題や、社会格差、ジェンダーの問題等を違う見方で考えられるのではないか、というひとつの提案ができればと考えています。

展覧会「ファルマコン:連鎖/反応」(2020, アトリエみつしま, 京都)展示風景.
写真左: 入江早耶《青面金剛困籠奈ダスト》(2020).
写真中央: 谷原菜摘子《パパが神様になったので》(2014).
写真右: 堀 園実《ごろごろとイモアラウ》(2020).
数年前からイタリア人の哲学者エマニュエーレ・コッチャ(Emanuele Coccia, 1976-)に注目しています。たとえば、彼を著名にした『植物の生の哲学』(《La vie des plantes》, 2016)において、コッチャは植物の生のあり方を「浸り(immersion)」というふうに言うんですね。「環世界(unwelt)」の概念を提唱したユクスキュルや人類学者のティム・インゴルドの説く生のイメージとも親和性のある考えです。また『メタモルフォーゼの哲学』(《La métamorphose》, 2019)も「わたしたちはただ一つの同じ生である」というテーゼを繰り返し主張している。植物のことを語っているようで、実際は動物や私たち人間まで含んでいるところがあり、ある種の希望を感じています。
マルチスピーシーズ(複数種)やポスト・ヒューマンの問題、人間じゃないモノの生を想像することができ、ある意味では、非人間やモノをアクターと考えるブルーノ・ラトゥールの思想とも繋げることができます。「ファルマコン」と同様に二元論を乗り越えて、そもそも世界を流動的な存在として捉えることができる。対話を打ち切らない考え方なんじゃないかなって思っていて。
理論的な研究として「共感」に取り組んでいく際、これらの言説を手がかりにして、人間の認識の枠組みを越えた次元から見てみようと、エコロジーについて考える芸術実践と書き物に今は関心をもっています。
異なる表現同士を結びつけるキュレーションの実践
- 最近のご活動では、ライフワークとして展覧会シリーズを継続開催されていて、研究に加えてキュレーションなどの制作的な実践も増えていますよね。
2017年からは、「ファルマコン」の展覧会シリーズを日本で年に一度ほど企画してきました。コロナ禍も休まず続けて、2023年に開催した回でこれまで7回開催しています。毎回、「ファルマコン:○○」といった感じで、その回で特に焦点を当てるテーマをサブタイトルで示すようにしています。医療、エコロジー問題、芸術と毒、身体の問題、生と死…、基本的にはこれまでお話ししてきたような問題を継続して考えているものです。特に、2021年の「死生への捧げもの」、2022年の「新生への捧げもの」では、一貫して「捧げもの」をテーマにすることで、現代社会の死生のありかたについて問題意識をもっていることを前面に出しました。
そうそう、2017年開催は京都・大阪同時開催で、医療とエコロジーの領域における芸術的感化をテーマにしたもので、参加作家が9人もいて、うち5人がフランスからの参加。ポーラ美術振興財団と朝日新聞文化財団からの助成していただくことができて、とにかく全力でやりました。全体のオーガナイズが大変でしたが思い出深い展覧会です。一度やってみたら、面白いなと思ったんです。やはり別々の作家だから、個人個人の表現や背景が違っていて、問題を共有できていなかったりする部分があるのはわかっているんですが、その表現を全体の文脈、自分がつくった展覧会のコンセプトの中でどんな風に見せるか、やりがいを感じましたし。キュレーションには専門のテクニックもあるし、その良し悪しについてもいろんな判断基準があると思うんですけど、異なる作家をあるテーマで結びつける部分に腕の見せどころみたいなものがあると思います。
過去にも、美術の批評を書くことに関心があって、可能な限り展覧会を見に行って、たくさん調べてブログなどでレビューを書くということをしていて、作品を見る視点とか作家を理解する視点を提示するという役割は魅力的に感じていました。
- それまで執筆の方でされていた批評的な観点の提示を、現実の展覧会として具現化する部分に面白さがあったんでしょうか?
そうですね。でも、ただ決まっている枠組みの中に組み合わせるだけではなくって、構想段階から作家と協働して展覧会を作り続ける、変化させ続けることができると少しずつわかってきました。
2023年の展覧会はフロリアン・ガデンと堀園実の二人展で、規模としては決して大きくなかったということもあって、作家の彼らも結構ストレートに意見を出してくれたんです。最初、私の方の思惑を提示するんだけど、「いや、それではちょっと」みたいに作家の意向がコミュニケーションされて、作家同士の議論によって作品が変わったり、彼らの新しいアイディアによって展覧会の全体像が変わるという経験をしました。それはあまり大きくない規模だからできたことですね。
もちろん今までも、ひとりの作家に対して「このテーマでお願いします」と依頼させてもらって、キュレータである私と作家が話し合う中で、出展作品を決めたり展示場所を検討することはあったんです。でも、今回のケースだと、作家同士が自主的に話し合って、変えちゃったわけですね。キュレーションにも介入してもらって、みんなで展覧会の方向性を決めていく、それがとても良かったと思います。
- こちらの研究室にあるたくさんの鉢植えも、次の展覧会に出展される作品とのことですね。どのような展覧会か教えていただけますか?

Jean-Louis BOISSIER 《crassula ubiquiste》(1985-)部分、大久保美紀研究室にて
はい。京都の西枝財団から助成を受けて、瑞雲庵という伝統建築の会場で「遍在、不死、メタモルフォーゼ」をテーマに日仏のアーティスト6名のグループ展を開催します。IAMASに関係する作家、フランス在住作家も参加します。
先ほどお話ししたコッチャの「メタモルフォーゼ」の哲学、「あらゆる生はただ一つの同じ生である」というテーゼから着想を得た展覧会なんですね。見た目こそ異なれど、あらゆる種は実際には異種混交の結果、生じてきたもの。こうした他の種、広い意味での生命を想像することが、生態系や気候変動のある現代の人新世のエコロジーを考える時に重要な視点を与えてくれるだろう、というストレートな内容になります。わたしたちがどこから来たのか、どこへ行くのか考えていく点で、過去にも未来にも繋がっています。
この鉢植えの作品は、出展作家の一人、ジャン=ルイ・ボワシエによる《crassula ubiquiste》(遍在するクラッスラ, 1985-)です。作家が世界中の旅行先・滞在先で出会った「カネノナルキ(学名はクラッスラ)」を挿し木にして持ち帰り、自宅で育てているものです。「カネノナルキ」は世界中どこにでもあり、かつ挿し木で人工的に育てるので完全なクローンであり、実は同じ種なんですよ。勝手に人の欲望が反映され、世界中に種が移動しているのも興味深いです。同じ個体を増やしているとも言え、死んでも死なない、総体としては偏在するものという点では、展覧会を象徴するような作品と考えています。今回は、これまで作家が育てていたものと、日本での滞在期間に東京と京都で新たに得たもの、合わせて12個の鉢植えを展示する予定です。
ボワシエは1945年生まれのメディア・アーティストでインタラクティブ・アートの先駆者として知られていますが、彼は近年こうした植物の生やコミュニケーションに着目した作品、人類学的観点から蕎麦猪口を扱った作品プロジェクトに取り組んでいます。こうしたメディアの捉え方は、私がつねづね大事にしているメディア概念に深く共鳴するものです。彼の作品では、カネノナルキや蕎麦猪口が、物事についての私たちの認識を揺るがすようなメディアとして振る舞っています。
「メタモルフォーゼ」のテーマで6名のかなり異なる作家を結ぶ展覧会で、どんな取り組みとなるか、ぜひ期待してほしいですね。

展覧会「遍在、不死、メタモルフォーゼ」
会期:2024年4月27日〜5月26日
会場:瑞雲庵(京都)
https://artsensibilisation.com
- IAMASではどんなことを学生に伝えたいと思いますか?
最近は、エコロジーについて言及するような美術表現や展覧会が増えてきていると思いますが、IAMASで学ぶ作家には、「エコロジー」の意味するところをよく理解して、表現として何ができるかということを考えてほしい。そのために、多角的に伝える意義を感じているんですね。やはり、エコロジー概念というのは、狭い意味での表層的な環境の話ではないということ。
授業の中では、アイ・ウェイウェイのような社会問題をテーマとする活動家について紹介したり、IAMASアカデミー出身でおられる高嶺格さんの展覧会「高嶺格のクールジャパン」(水戸芸術館現代美術ギャラリー, 2012)を始めとする多領域にわたる問題提起に言及するなど、具体的に作家や展覧会を紹介することもあれば、思想史的にエコロジーがどのようにとらえられてきたか参考になる文献を一緒に読むこともあります。そういう視座を持って問題をとらえることで、作家になろうとしている人にアイデアをあげられるのではないかと考えています。
「メディア」という言葉についても同様ですね。この言葉は、いうまでもなくニューメディアだけを指すわけではなくて、マーシャル・マクルーハンがいったような意味で、認識の枠組みや感覚すら変えるような働きそのものを表しています。先ほどボワシエの作品についてお話しした際にも少し触れましたが、「メディア」や「メディア・アート」という概念について、自分の中で深く考えられているかどうかで表現は変わるはずです。
「技術」について言えば、コッチャは「繭としての技術」という言い方をするんですよ。「メタモルフォーゼ」の哲学は、昆虫の変態の話をエコロジーに応用しているかのようだけど、実は重要なのは技術の話です。たとえば受精卵においては未分化であった細胞が、やがて卵の中で成長し、鳥のヒナになって生まれてくる。これが技術です。一冊の本を読んで私たち自身が影響を受けたり変化したりすること、あるメディアを通じて感覚そのものが一変するというようなこともまた技術であると考えられます。
「技術」を人間のコントロールできる道具として思考するようなテクノロジー観が、現代文明の行方の根源にあると思うんです。「繭」という比喩は、そういう近代的な技術哲学、テクノロジー観をひっくり返せるような技術の捉え方であり、自分で自分のことを変容させる技術のことを表しています。ちなみに、IAMASが岐阜県美術館で関連作家を紹介するIAMAS ARTIST FILEという展覧会が一年に一度あるのですが、2024年度は「繭」をテーマに企画して、私が企画を担当しています(「繭:技術を思考するエコロジー」2025年1~3月岐阜県美術館で開催予定)。これは、「テクノロジーの〈解釈学〉」というIAMASのプロジェクト研究の一環で行います。学生にも積極的にコミットメントしてもらいたいと考えています。どのような「協働」が可能となるか、楽しみです。
テクノロジーは広い意味での「技術」の一部でしかない。そして《art》は「芸術」と「技術」の両方を意味しますよね。今日、テクノロジーは先端化・専門化した技術という意味において一義的に捉えられてしまいがちですが、元をたどればもっと広く「アート(つくること、技芸)」に通じている。そんなふうに、今日の固定概念を取り払って根源的に考えてみる態度を、授業や展覧会等の実践で共有していきたいと思います。

大久保美紀 / 准教授
デジタルディバイスを通じて実践される様々な自己表象行為について、身体意識やアイデンティティの観点から研究を行う。芸術の〈共感〉可能性と、両義的な概念〈ファルマコン〉に着眼し、新しいエコロジー思想のためのキュレーション・作品制作を行う。「共感論」を拡張し、器官学に基づく技術観を乗り越える新たなエコロジー美学の構築を模索する。
インタビュー実施日:2024年1月12日
インタビュアー・編集:はがみちこ
撮影:福島諭(産業文化研究センター[RCIC]研究員)

