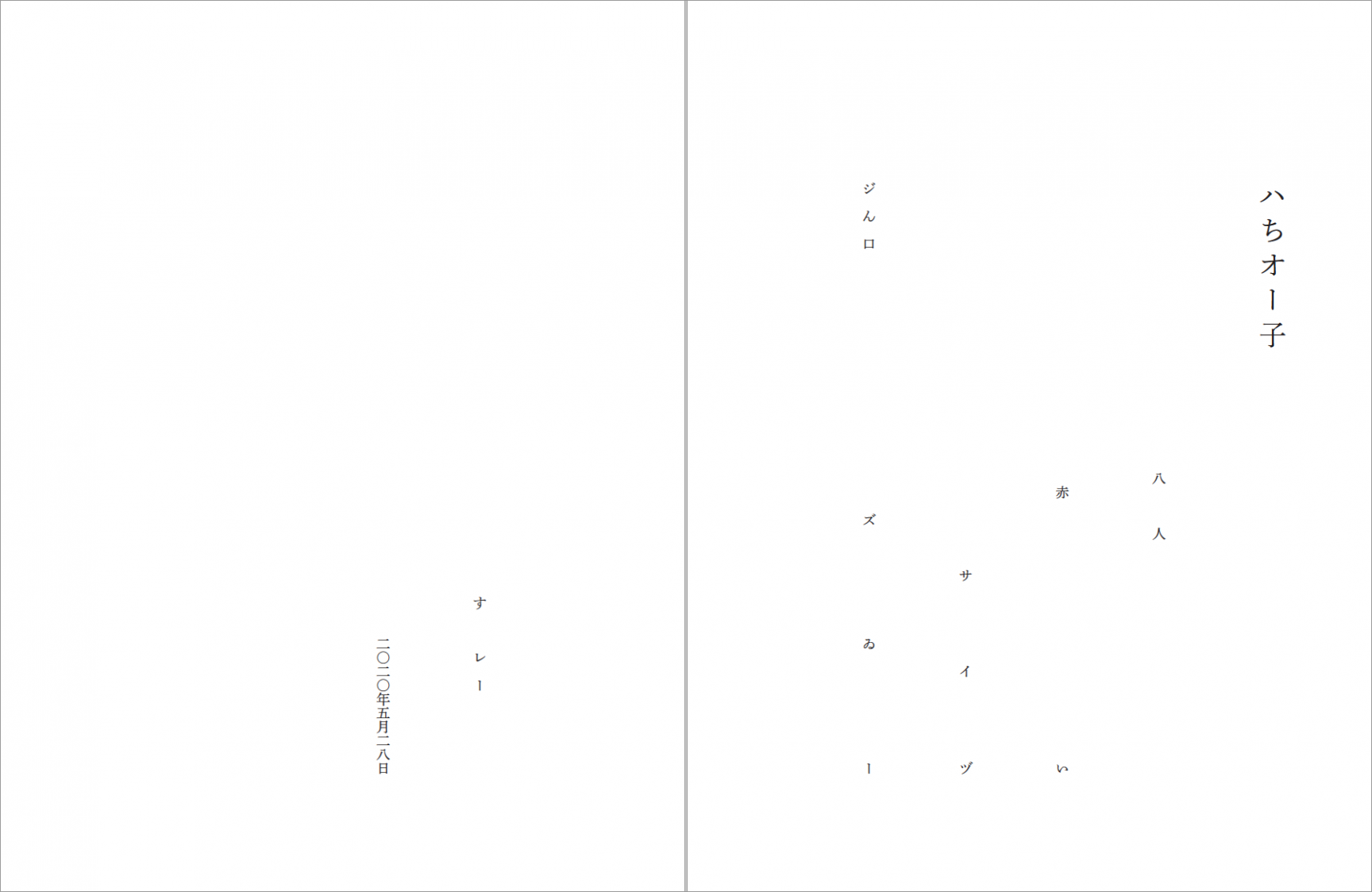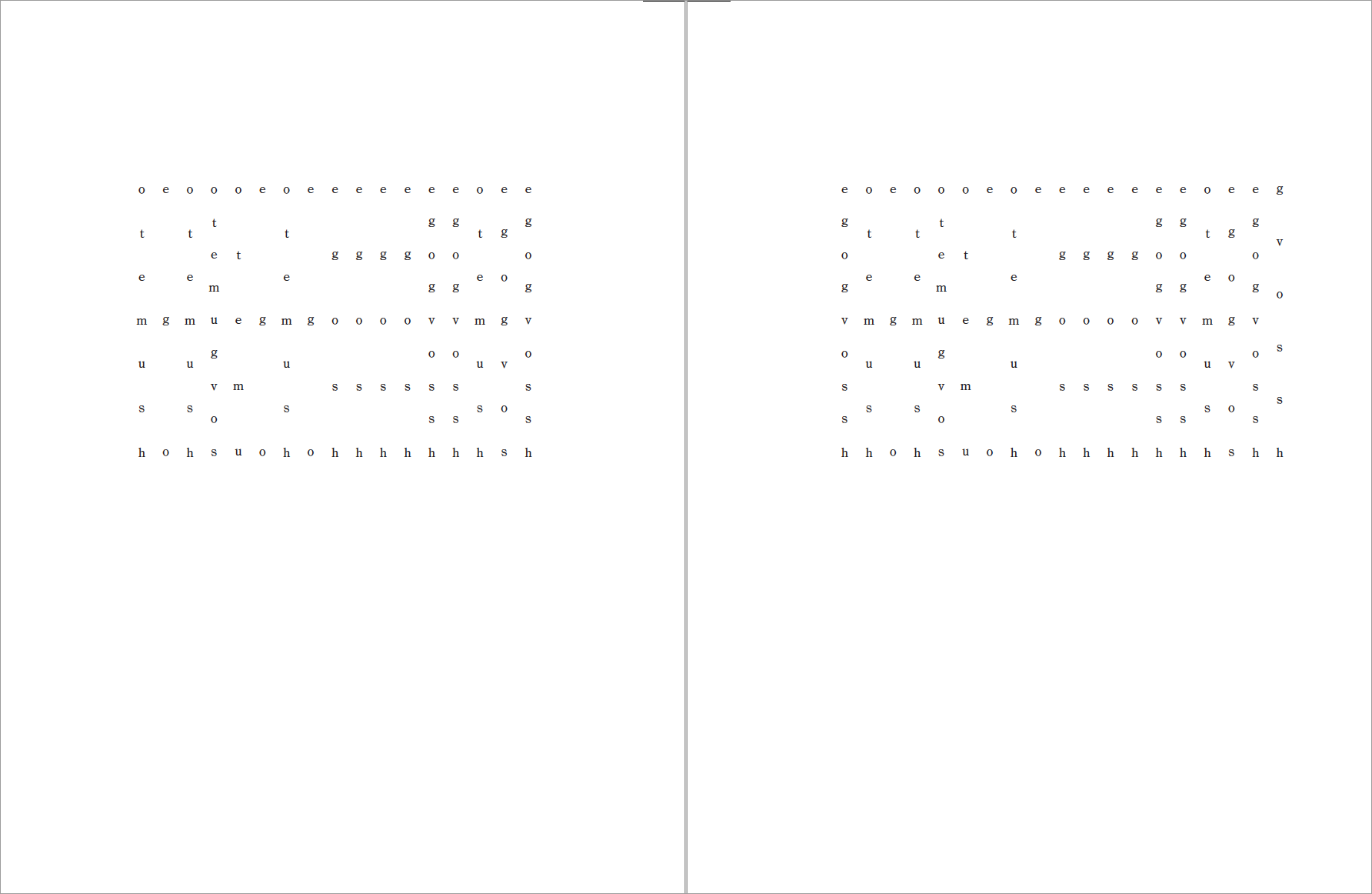教員インタビュー:松井茂准教授

マスメディアを通して戦後日本美術を捉え直す
- まず、研究内容の「映像メディア学」について教えてください。
2005年、東京藝術大学大学院映像研究科が設置されたとき、映像メディア学という学術領域を自称したんですね。英語だと「film and new media」。そんな時期に、映像研究科長だったメディア・アーティストの藤幡正樹さんに誘われ、僕は大学に勤めるようになりました。それ以前は編集者をしていたので、専門的な研究者として大学で仕事を始めたわけではないんです。たまたま大学に新しい研究分野が立ち上がるときだったことも幸いし、芸術における学術領域のあり方を、藤幡さんとの会話や、たまに任される授業のなかで考えていく機会を得て、自分の関われる研究を探した感じです。
藤幡さんは、80年代にテレビメディアで作品をつくったことがあるんですが、メディア・アーティストとしての活動の背景には、インターネットメディアの前身に位置づけられるテレビメディアへの関心があって、僕はこれに興味を持ちました。あるとき、テレビマンユニオンの創設者のひとり、村木良彦を主題にしたドキュメンタリー番組(是枝裕和がディレクターを務めた『報道の魂 あの時だったかもしれない』2008年)を紹介してくれたことがありました。この番組は、僕がテレビメディアの研究にあしを踏み出す大きなきっかけになりましたね。
テレビのことって、現在のインターネット同様、自明過ぎて気にしてこなかったのですが、振り返ってみると、個人的な経験もいろいろあったんですよね。つまり中高生だった80年代後半から90年代前半に、テレビを経由してアートシーンに接していましたし、普通に世代毎にそういうことはあると思うんですが、いろんな番組を記憶しているんですね。当時は、NHKの番組で現代詩が紹介されたり、パフォーマンスみたいなこともあって、いま見るとすこしダサいのですが、ラディカルでした(『ナイトジャーナル』1993〜94年、NHKなど)。表現として尖ったもの、マイナーなものがカルチャーとして先にあるのではなく、非常にメジャーな入口からマイナーが見えてくる体験をしていたと思います。
現代美術の世界では、マスメディアを肯定的に語ることは恥ずかしい気がしますよね(笑)。でも、自分の経験に限らず、特に20世紀後半のアートは、無自覚になるくらい強力にマスな視覚文化が前提にあります。戦後、アートシーンの中心がヨーロッパからアメリカに替わってポップアートが登場するとき、これが世界的な共感を得た背景には、アメリカが牽引するマス・コミュニケーション(大量伝達、大量生産、大量消費)の力があった。それが視覚や認識のなかに価値観として刷り込まれている。ある種の世界的な同時性として、ポップアートやその後のメディアアートを受けとめる認識論が、メディアによって知らず知らずのうちに身体化されてきたということ。テレビやインターネットは、良くも悪くもそのサーキュレーションのインフラで、そこに表現が生まれてきたことを考えたいというのが、僕にとっての「映像メディア学」です。
- 今年3月には、著書の『虚像培養芸術論 アートとテレビジョンの想像力』が出版されます。戦後日本美術について、いわゆる前衛の歴史やイズムの交代史ではなく、マスメディア(放送文化と出版文化)という視座から捉え直すという企図の本ですね。
 『虚像培養芸術論-アートとテレビジョンの想像力』(フィルムアート社)
『虚像培養芸術論-アートとテレビジョンの想像力』(フィルムアート社)タイトルの「虚像培養」という言葉は、60年代に美術批評家の東野芳明(1930〜2005年)が、「イメージ・カルチャー」という言葉を禍々しく、面白おかしく訳した言い回しだと思うのですが、今で言うと、「表象文化」という言葉に近いと思います。東野の「イメージ・カルチャー」論を手がかりにすることで、美術だけでなく、建築やテレビ番組などを並列的に考えていくことで、通常の戦後日本美術とは違う切り口が見出せるんじゃないか? アートの訳語としての「美術」ではなく、近年の美術館がアートを原語通り、芸術全般と再定義したような展開をしていますが、そうした意味でのアートとして60年代を取りあげています。「アンダーグラウンドな表現が先にある」という考え方をいったん捨てて、マスメディアがむしろアヴァンギャルドであるとし、作家もまた大衆の側の目線を前提としていることから考える思考実験だと考えています。このことは、現代のメディアアートやインターネットのカルチャーを考える上でも重要なことです。つまり本書は、60年代論でありつつ、2010年代のメディア環境についての批評でもあります。2011年は、東日本大震災の年ですが、テレビのアナログ放送が終了した年でもあります。そしてテレビ放送のインターネット配信、ストリーミングが急激に一般化した時期です。その状態は、1950年代にテレビ放送が始まったときのような、視覚文化の大きな転換点だったと思います。こうした現在を直接的に扱う前に、まずはオールドメディアと呼ばれるアナログ放送の視覚文化を問い直すことが、現代を批評する土台になると考えています。
- 「視覚文化の大きな転換点」ということですが、アナログ放送からデジタルへの移行は、どこが根本的な変化でしょうか?
1980年代にデジタルメディアが「ニューメディア」だと言われ、インターネット元年と呼ばれる1995年以降は、インタラクティブなメディア環境が普及していきました。ただ、人々が概念としてではなく、本当の意味でこうしたメディア環境を享受してきたかというと、結構微妙だと思うんです。掲示板などサブカル的なインターネットのカルチャーはありました。僕はそこへの着目ではなく、誰もがスマートフォンを持ち、YouTubeのような動画共有サイトやSNSを急激に活用しはじめた、映像とテキストを併用したコミュニケーションの手法を体得した、2010年代に興味をもっています。人々がデジタル環境を使いこなすなかで、1960年代に続いて、生活レベルでイメージの流通革命が起こっている気がしています。このタイミングは、日本で言うと東日本大震災をめぐるメディア状況、世界でいうとジャスミン革命あたりでしょうね。1980年代や、強いて言えば70年代頃から、概念としてはデジタルメディアに関する言説は多くありました。しかし技術的な発明と、それが成熟していく時間にはタイムラグがあります。また、そこに芸術表現の分野が見出されるのには、さらに時間的なズレがありますよね。
僕にとっての新しい現象というのは、完全に淘汰されてしまう技術とそうでない技術があるわけですが、意外に絶滅しないで複数の技術が共存している状態で起こる現象なんです。60年代であれば、テレビの普及によって人間の認識論が変わり、美術や建築が影響されるいっぽうで、映画が没落していきます。しかし完全に絶滅することはないですよね。いまもある。するとテレビと映画はお互いを差別化し合いながら、新たな表現をつくっていく。完全に淘汰されないところで、似た技術を持った分野が、技術史的な順番と異なる表現方法の歴史を築いて競り合うわけです。そうした反転や、並走状態に注目することで、特定の定義に基づくアートを探すのではなく、自然発生的に生成される表現の多様性や意味の差異の分析として芸術を考えることができればと考えています。
オンライン展覧会によって、制度が作品を規定する状態を打破できないか
- 3月末予定のオンライン展覧会「メタ・モ(ニュ)メント2021/Meta mo(nu)ment 2021」 ※1を企画されています。企画趣旨を読むと、美術館やギャラリーといった既存の美術の制度に対する批評的な観点が書かれています。このことは、先ほどの、マスメディアの視点から現代美術を捉え直すこととつながっていると思います。
これはArchival Archetypingという、小林茂さん、クワクボリョウタさんと担当しているプロジェクトの企画です。この展覧会というかイベントが前提としていることを説明します。
例えば、美術批評家のクレア・ビショップが『ラディカル・ミュゼオロジー つまり、現代美術館の「現代」ってなに?』(月曜社、2020年。原著、2013年)で指摘していますが、近年、展覧会でも作品でもなく、美術館という建物が前面化していると。そこを問うことができるという意味で、オンライン展覧会は、ひとつの方法論になると思うのですが、2020年のコロナ禍以降の動向を見ていても、リアルなミュージアムの代替以外の展開が無かったことに問題意識を持ちます。もちろん、収益を上げないといけないインスティテューションや作家たちがいるわけだから、ビジネスになることも必要だと思います。でも、アートの制度や作品概念について考える立場から、ハードウェアの制約がそもそも存在しないオンラインであればと考えた瞬間、美術館や展覧会という枠組み、作品を作品たらしめている問題が前景化できるのではないか? 制度論が問うてきた枠組みというとオーバーですが、自分の批評のモチベーションにかかわる問題提起が実践できるのではないかと思いました。ですから、コロナ禍なのでオンライン展覧会をやりたいと思ったというより、批評としてオンライン展覧会という戦略があったことを、今の状態が教えてくれた感じです。
こうした問題意識の実践にこそ、メディアテクノロジーが本来もっている、良い意味での野蛮さが使える。僕は基本的に「メディアアート」という言葉を使わないのですが、もし積極的にその言葉に意義を持たせるのだとすれば、現実の制約を解体した問い直しが表出できる芸術様式だと定義したいですね。
いっぽうで、これは宿命かもしれないけど、ストリートアートやインターネットアートの文脈から出てきたり、制度を侵犯するような表現をする作家が評価されていくと、美術館で大きな個展をやったりコレクションに加えられたりする。社会制度のなかに自分の作品を混入させることで、芸術概念や社会制度を変えていくという動きが歴史化されていく。それは同時に、批判対象である美術館という制度にコレクションしやすいかたちで脱色化されて、一つの安全な様式になってしまう。それを二番手、三番手で継続する作家は、芸術の裾野をつくっているのだし、悪いわけじゃないんだけど、実際には消費者だと思います。様式をこなすのではなく、自分でルールをつくっていけることが作家性だと考える状態をどうしたら醸成できるのか? この問題は、アートを考えるときに陥りがちなトートロジーです。僕は、前衛もどきでもなく、消費者でもない、大衆(マス)の無意識を相対化したところに現れる作家性や作品概念に着目したいと考えています。
きっと、僕たちが今、作家とか作品だと全く思っていないところに、新しい表現者や、これまで知らないような様式や形式が現われているのではないかと思います。今はまだ、自分たちの準拠枠には入っていないだけ。例えば、YouTuberが、数十年後に展覧会で振り返られたりするのかもしれません。ただ、教育は、常に制度の後追いでしかなくて、それを教えると常に二番煎じの消費者をしたてあげてしまう。大学はその限界を自覚する必要があると思います。ただ、その自覚を教えられるのが批評の役割なんだと思いますね。
インターネット上に発表することで、「詩とは何か」を反省的に考える
- 最後に、詩人としての表現活動についてお聞きします。新聞朝刊の気象情報を5日間ごとにメール配信する「量子詩」、Facebook上に発表された詩をまとめた『二●二●』など、表現形式に加えて、「詩」の発表媒体についての問いも含まれていると思います。いわゆる現代詩というと、文芸誌がオーソドックスな発表形態ですが、誰でも無料で見られて、複製や転送も容易なメディア上で発表されています。
美術館の制度と同じで、文芸誌に載せればなんでも詩になるという現代詩の流れはずっとありました。でも僕は、本来、芸術って、極端なことを言えば荒野のなかにポンとあっても、「これは作品だ」と言えないとだめだと思っているところがあります。ここまで話したことに矛盾するかもしれませんけどね(笑)。僕がホームページを作って「純粋詩」という作品を発表し始めて20年が経ちます。2001年当時、インターネットは好き勝手に「作品だ」と主張して発表できる場所であるいっぽう、他のいろんな情報と並列化されてしまうので、この荒地で詩を書くとはどういうことなのかと、芸術を定義するにはうってつけの場所でした。「詩とは何か?」を考えないといけなくなる。インターネット上で表象することは、自分のしていることは何なのか? 厳密な定義と制御が常に求められる。それはいまも変わりませんね。僕にとっては。
ホームページやメールに続いてSNSが登場しましたね。SNSのようにプラットフォームとして用意された場においては、「このプラットフォームは作品の支持体になりうるのか」を考える必要が出てきます。「正しい」使用法と、なんらかの条件が用意されているからです。「メディアのコンディションを考える」というのは藤幡さんの言葉ですが、自分の作品を発表すること自体が、池に石を投げて波紋を観察するようなことでもあり、リアクションを見ながらメディアの状況を探るみたいなことだと思うんです。マーケティングとは違うんですけど、僕は20年間くらいそんなコミュニケーションを続けています。
そんななかで、長年つかっていたtwitterとFacebookを2019年の夏にやめました。それが、2020年の春、コロナ禍でアートシーンがどうなっているのかだとか、友人達の大学はどうしているのかという情報を得るために再開したんです。それでFacebookを支持体にした詩を探ってみようと、2020年の3月から6月まで「メディアのコンディションを考え」てました(笑)。程なく、電子音楽研究者の川崎弘二さんの計らいで、詩集『二●二●』として刊行できました。オンラインから紙媒体への置換の意味も考えなくてはいけないですが、そこはこれからですね。
他方で、Facebookを支持体として成立した詩集に対して、フランス文学者・メディア情報学者の石田英敬さんは、わざわざtwitter上に批評を書いてくれました※2。僕の詩の背後にある歴史的文脈を解読したわけですね。インターネットが歴史を並列的に情報化して耕し続けている感じがしました。リミックスされたような感じでとても面白かったです。石田さんを媒介に、僕は僕なりに、エドガー・アラン・ポーやマラルメ、無意識に選択してきた言葉の背景を知り、ネットワーク上で先人たちと対話していることを確認しました。作品とは、僕自身も含め、すべての人が読者であることを前提とした世界であると考えると、突然霊感的なものが降ってくるのではなく、すべてが疑わしいオリジンに基づくリミックスであり、歴史の網目のなかで差異化されていく行為が意味を生成していくのだと、改めて思いました。こういう感覚を共有していきたいですね。

松井茂 / 准教授
1975年東京生まれ。著書に『虚像培養芸術論 アートとテレビジョンの想像力』(フィルムアート社、2021)。詩集に『二●二●』(engine books、2020)等。共編に『虚像の時代 東野芳明美術批評選』(河出書房新社、2013)等。共著に『テレビ・ドキュメンタリーを創った人々』(NHK出版、2016)等。監修に『美術手帖』の特集「坂本龍一」(2017)、「平成の日本美術史 30年総覧」(2019)、『現代思想』「磯崎新」(2020)等。キュレーションに「磯崎新12×5=60」(ワタリウム美術館、2014)、「磯崎新の謎」(大分市美術館、2019)等。プログラム「藤幡正樹 Expanded Animation Works」(恵比寿映像祭、2014)等。
※1 メタ・モ(ニュ)メント2021
https://archival-archetyping.github.io/meta-mo-nu-ment-2021/
※2 石田英敬「Matsui Hacking Project」──詩集『二●二●』評
https://www.iamas.ac.jp/report/matsui-hacking-project/
インタビュアー・編集:高嶋慈
撮影:山田聡