マス・メディアに読む脱中心化の思考——共同研究「マス・メディアの中の芸術家像」第4回研究会レポート

2019年12月26日から27日にかけて、本学にて共同研究会「マスメディアの中の芸術家像」第4回目が開催された。この研究会では、テレビがほぼ100%普及した1968年からインターネット元年と言われる1995年までをひとつの時代区分と捉え、オールド・メディア成熟期に生まれた新たな芸術家像の特徴を描き出そうとしている。第4回目を迎えた今回は、映像、批評、詩が交差する地点にマス・メディアの中の芸術家像を探る試みとなった。
1日目の基調講演は、前田真二郎の「ヴィデオと自作をめぐって」、Ken Yoshidaの「Toward a Critique of Global Contemporaneity in the Japanese Art History of the Present」、坪井秀人の「ストリート文化のなかの寺山修司」。2日目は、藤井貞和、坪井秀人の対談による「湾岸戦争論とはなんだったのか?」。1日目の基調講演を中心に、研究会での発表、ディスカッションについて報告する。
マス・メディアの中に個人の映像表現を読む
前田真二郎は、「映像表現史1968-1995—1969年生まれの映像作家による—」と題して発表を始めた。自身がテレビから受けた影響に始まり、マス・メディアの構造に一石を投じた映像作品の系譜を振り返ることにより、作品発表を始めた90年代初頭の映像をめぐる状況を浮かび上がらせる意図があったと考えられる。
インターネットで映像を視聴することが当たり前となった現在、テレビの視聴を取り立てて有害視することはなくなったが、テレビ受像機が普及した60年代後半には新しいマス・メディアの形態であったが故に、テレビ放送の弊害がしばしば指摘されてきた。例えば、テレビの映像は反復的であり、不特定多数に向けた一方通行の情報発信である点、対面のコミュニケーションではなく、日常生活の時間を切り刻むという点で、非人間的なメディアとして危惧されていた。その一方で、テレビは常に新しい映像表現の実験場になっていたのも事実である。前田が例として挙げたのは、子どもが見るテレビ番組だ。1966年に放送が開始されたウルトラマンシリーズは、特撮で知られるが、合成、スローモーション、オーバーラップ、光の表現などにより、映像の作り手の意図や仕組みを受け手が読みこむ余地がある。同時期、すでに大衆的なメディアとして定着していた映画もまた、新たな方向性を模索していた。従来とは異なる方法、形式で上映される「エクスパンデッド・シネマ」もそのひとつで、松本俊夫の《つぶれかかった右眼のために》(1968年)は、3面マルチプロジェクション、ストロボによる光の演出を含む作品として発表された。テレビの普及により、既存のメディアの布置状況が変化しつつあったことが窺える。
ここで私が思い起こすのは、1971年3月に、グラフィケーション別冊として出版された『複製時代の思想』(富士ゼロックス株式会社)だ。多田道太郎が寄稿した「複製芸術とは何か」には、同時期のマス・メディアと表現の関係が示唆されている。
「ベンヤミンは、儀礼から展示への転換を指摘した。わたしは更に、展示から伝達への転換を指摘したい。送り手側から言えば伝達の拡大、受け手側から言えば、伝達されることの自由。芸術は例えば、ムード音楽となり、わたしたちの「散漫」な耳に囁きかける。緊張は無意味である。緊張とは作品の美に到達し没入する際の準備だからである。わたしたちにとって美は存在するか。美は存在しない。芸術における儀礼から展示へ、展示から伝達への変化は、一般社会における「聖」から「俗」へ、また「俗」から「遊」への変化に照応している。「聖」のおそろしさから自由な世界を「俗」だとすれば、「俗」の窮屈さから自由な世界が「遊び」である。わたしたちは美の世界ではなく決定的に自由な世界に生きているのである。
しかし皮肉なことに、このスプーン・フィーディングの自由は、スプーンを口元まで運びミルクをそそぎ込んでくれる巨大な商業組織、機械機構によって支えられている。このメカニズムを改変することはわたしたちの「自由」ではない。それは個人の力の及ばない超越的な何物かとしてわたしたちを威圧しつづける。
(中略)わたしたちは決定的に不自由な組織の中で、組織に包まれながら決定的に自由な空気を吸っている。この逆説的な事態こそが、複製芸術に生気を与えるものである」。
多田道太郎「複製芸術とは何か」『複製時代の思想』(富士ゼロックス株式会社、1971年3月)141-142頁。
多田の指摘を踏まえるならば、テレビが私達の日常にもたらした「逆説的な事態」を受け止めた先に、映像表現が成立してきたと言っても過言ではないだろう。前田が紹介した、鈴木志郎康《草の影を刈る》(1977年)と伊藤高志《SPACY》(1981年)も、極私的な日常と映像メディアの構造を映し出すというそれぞれの方向性によって、マス・メディアを相対化している。
伊藤の《SPACY》には、若者向けのテレビ番組『YOU』の特集「撮った!見せた!ウケた? ビデオ」(1983年11月26日)で、その一部が放映されたという側面もある。『YOU』は1982年から87年にかけて土曜日の夜10時半から放映されたNHKの番組で、初代司会者に糸井重里、テーマ曲に坂本龍一、タイトル画に大友克洋が起用され、スタジオに招かれた約80人の若者とのトークなどが含まれる。当時の若者たちが《SPACY》をどのように受け止めたかを知りたいところだが、作品の流通と受容の関係が多層化していくことを考える上でも重要な事例であった。マスメディアと映像表現の関係の変化の延長上に、前田真二郎の《TELEVISION BY VIDEO BY TELEVISION》(1993年)を見直すことで、カラーバーや砂嵐というテレビ放送の視聴環境を相対化し、素材として扱うコンセプチュアルな手つきを読み取ることができた。
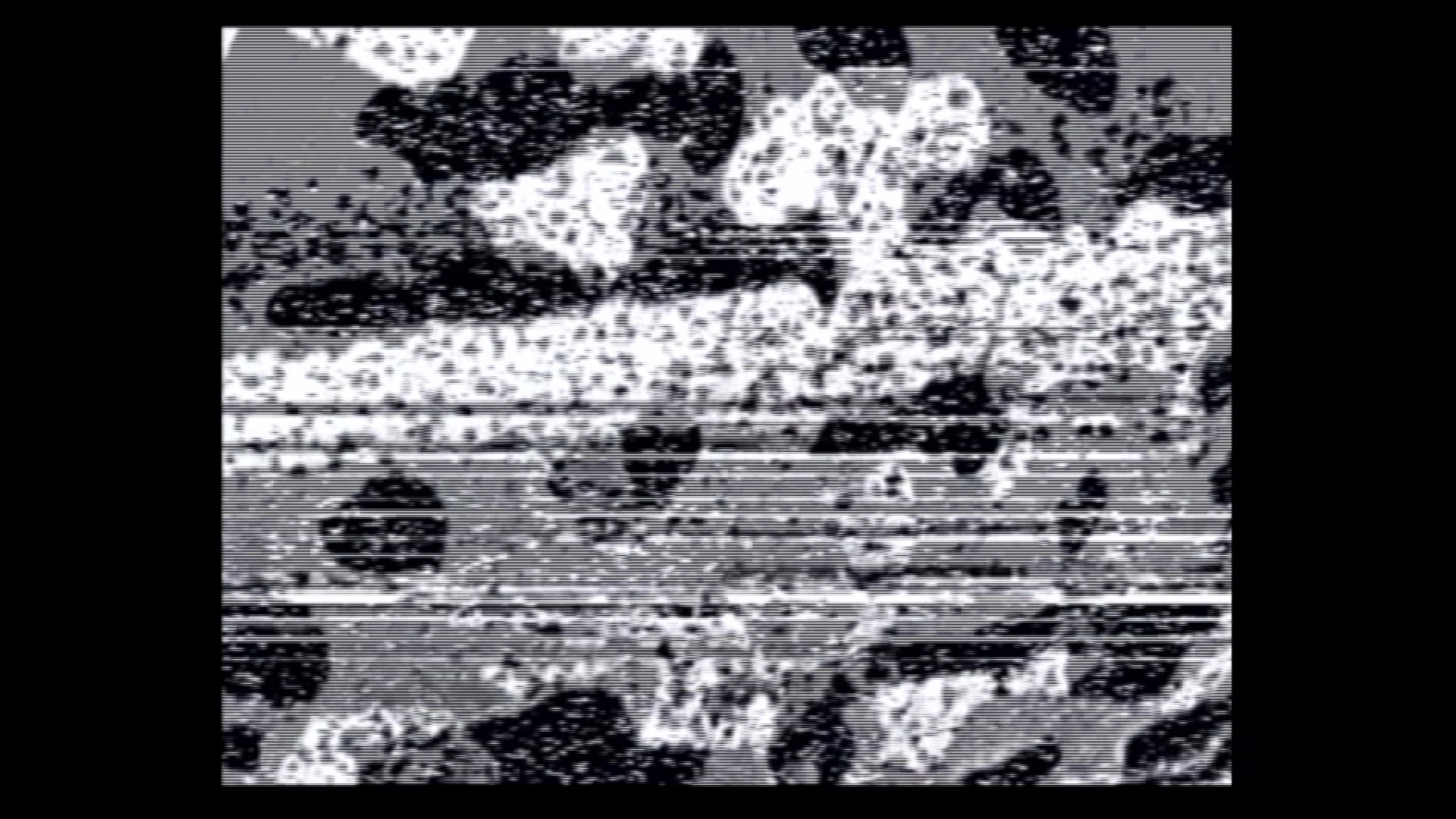
前田真二郎《TELEVISION BY VIDEO BY TELEVISION》(1993年)
日本の美術批評における脱中心化の系譜
ケン・ヨシダは、現代美術史の記述においてdecolonialの思想をいかに導入できるのかという視点から、千葉成夫、石子順造、宮迫千鶴の美術批評の再評価を試みた。アメリカの美術史観そのものが、ヨーロッパ中心の美術史を踏襲して形成されてきたが、その文脈の延長上に日本の現代美術を位置づけようとする時、非対称な関係が浮き彫りになることがある。一例として、ヨシダは富井玲子の「Radicalism in the Wilderness : International Contemporaneity and 1960s Art in Japan」(MIT Press、2016年)を挙げ、その役割を十分に評価しつつも、結果的に日本美術を「グローバルな」美術史の周縁に位置づけ、欧米中心の歴史観を強化する構造に加担してしまうことへの危惧を指摘した。とりわけ、「国際的同時性」を強調することにより美術史の通時性を担保し、「コピー(模倣)」をオリジナルへの追随として退ける価値観に疑問を投げかけた。これに対し、欧米中心史観の内面化を早期に自覚していた批評家としてヨシダが注目したのは、千葉成夫である。ヨシダは、千葉の「類としての美術」をグローバルな美術史を脱中心化する語り口として評価するが、同時に千葉の脱中心化への戦略は、その後の美術史の展開において、欧米中心的な言説に日本を取り組むための方法論としても機能していることを指摘した。その上で、むしろ石子のキッチュや「まがいもの」の概念を再読することに、グローバル化への志向を覆す批評性を見出した。今回の研究会では、その延長上に宮迫千鶴『イエロー感覚 不純なもの、あるいは都市への欲望』(冬樹舎、1980年)を再読し、80年代文化論につなげようというヨシダの意図が感じられた。同時期、谷川晃一が『アール・ポップの時代』(皓星社、1979年)を発表し、パルコ(池袋、札幌)で「アール・ポップ」展(1979年)を開催しているが、宮迫の「イエロー感覚」は、欧米からの影響がない交ぜになった日本人の主観を通して女性論や家族論を語っている点で再評価できるだろう。
寺山修司から考える戦後詩の射程
坪井秀人は発表の冒頭で、本研究会の歴史認識として「1968年」をどのように引き受けるかを問う必要があると述べた。複線として、1990年に加藤典洋と高橋哲哉の間で交わされた「歴史認識論争」があり、保守派と革新派がともに戦後責任を回避してきた「ねじれ」を、1968年を起点にどのように捉え直せるのか、「マスメディアの中の芸術家像」を通じて考えるねらいがある。その主題として坪井が選んだのが、「ストリート文化のなかの寺山修司」であった。
寺山は、1967年に『書を捨てよ、町へ出よう』(芳賀書店)を出版した後、1968年にはテレビ版を木島則夫ハプニングショーで上映、1971年には寺山自身が監督・製作・脚本を務める同名の映画を公開している。背景には、1967年に寺山が旗揚げした「天井桟敷」とアングラ演劇ブームがあり、「天井桟敷」の第7回公演(1968年)でも「ハイティーン詩集 書を捨てよ町へ出よう」が、演劇作品として発表されている。寺山は、すでに『思想』1960年6月号において、ラジオ・ドラマやアクション・ペインティングを引用して「アクション・ポエム」について述べているが、『書を捨てよ、町へ出よう』は日常性をテーマにアングラとマスメディアを往来し、メディア横断的に展開した側面を含めて、それを体現した作品と言える。「町は開かれた書物である、書くべき余白が無限にある」に象徴されるように、寺山の言葉は学生運動の機運を反映した直接行動の詩として受け止められ、近年の再評価にもつながっている。坪井は、寺山の詩人としての態度の中に荒地派への反発を読み取り、国家よりも「土地」として人間の営みを考え、故郷へ戻るという欲求を拒絶し、帰るのではなく「行く」ことを選択した志向性について分析した。
このような経緯を踏まえて、坪井が寺山の映画作品の中で注目したのは、《Laura》(1974年)であった。ストリップ小屋につくられたスクリーンで上映されたのが初出であり、エクスパンディド・シネマとして知られる作品である。そこには、演劇と映像のフレームワークを活かし、フィクションとリアルをつなげようとする寺山の関心が読み取れる。具体的には、スクリーンにスリットが入っていて、観客席に仕込まれた役者が引き込まれたり投げ出されたりすることによって話が展開する。メディアの構造を相対化し、観客の立ち位置を揺さぶる表現のあり方は、冒頭の前田の発表とも共通点があると感じられた。
三者の発表を通して浮き彫りになったのは、マス・メディアとの関係によって育まれた脱中心化の思考であった。2日目の藤井貞和、坪井秀人の対談による「湾岸戦争論とはなんだったのか?」は、『鳩よ!』(マガジンハウス、1991年5月)を中心とした反戦声明についてであった。同人誌とマスメディアにまたがる詩の論争の論点を振り返り、第5回目の研究会へとつなげた。

